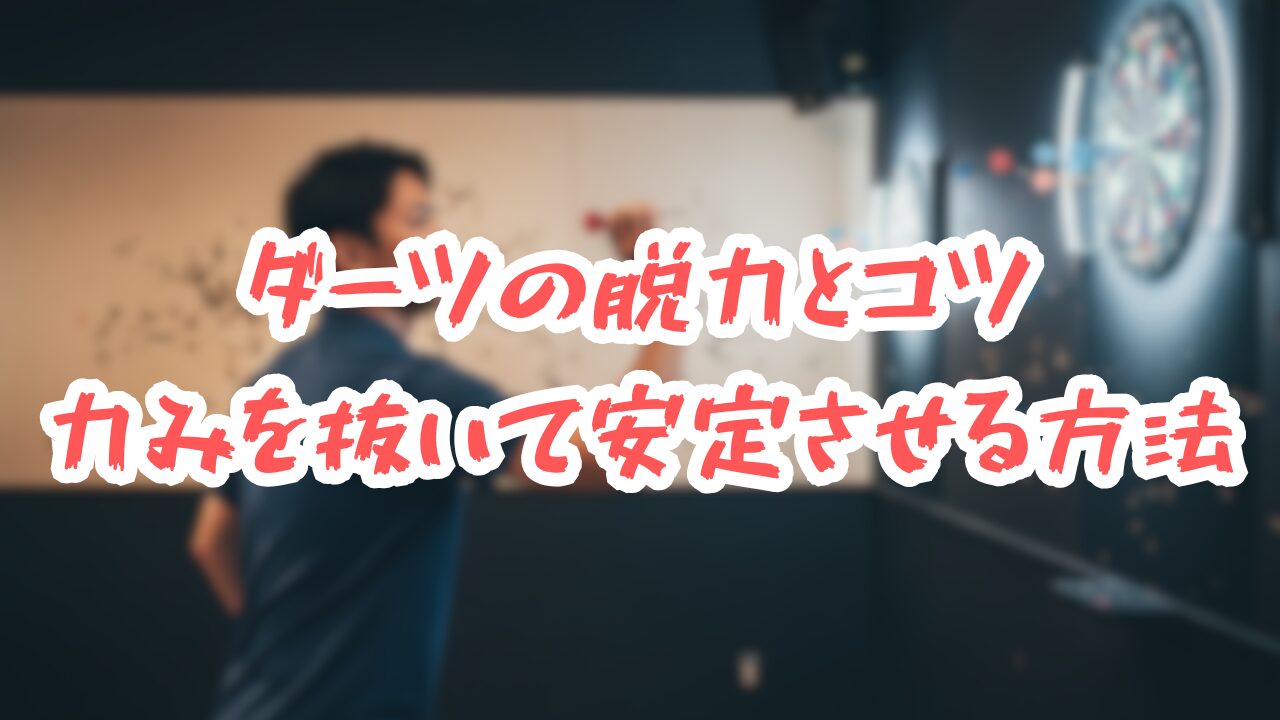
ダーツの上達を目指す中で、多くの人が「ダーツの脱力とコツ」というテーマに突き当たります。ブルを狙えば狙うほど、なぜか腕や肩に余計な力が入ってしまい、テイクバックで腕が固まる経験はありませんか。
上手い人の特徴を観察すると、その滑らかなダーツの力の伝え方や、無駄のないダーツの力の乗せ方に驚かされます。しかし、いざ真似しようとすると、セットアップの段階から力む、肩に力が入りすぎて肩の力みを抜く方法は?と悩む、といった悪循環に陥りがちです。
中には、ダーツを擦って投げる感覚が良いと聞いても、逆に脱力しすぎてダーツが飛ばない状態になってしまう方もいます。この記事では、そんな力みに関する悩みを解消し、技術として脱力を身につけるための具体的な方法を解説します。
記事のポイント
- ダーツで脱力が必要な根本的な理由
- 肩や腕など部位別の力みの原因と具体的な解消法
- 脱力を体に覚えさせるための効果的な練習ドリル
- 正しく脱力できているかを確認するセルフチェック方法
目次
- 1 再現性を高めるダーツの脱力とコツ
- 2 実践的なダーツの脱力とコツ【応用編】
再現性を高めるダーツの脱力とコツ

- 「力み」がダーツを不安定にする3つの理由
- 上手い人はなぜ力んでいない?共通するフォームの特徴
- 腕の重さだけで飛ばす「正しい力の伝え方」とは
- グリッププレッシャーを確認する簡単なセルフチェック方法
- 構えの瞬間から力が入る「セットアップ力み」の解消法
- テイクバックで「腕が固まる」原因と肘を柔らかく使う意識
「力み」がダーツを不安定にする3つの理由

ダーツにおいて「力み」は、上達を妨げる最大の要因の一つです。では、なぜ力むとダーツが不安定になるのでしょうか。その理由は主に3つあります。
1. 動作の再現性が著しく低下するから
ダーツは、毎回同じ動作を繰り返すことで的を狙う競技です。しかし、力加減というのは非常に曖昧な感覚であり、人間が毎回100%同じ力で腕を振ることはほぼ不可能です。
力を入れれば入れるほど、その日の体調や精神状態によって力の出力が微妙に変わり、リリースポイントやダーツの軌道にズレが生じます。これが「昨日は入ったのに今日は全く入らない」という状態を生む大きな原因です。
2. 体の不要なブレを引き起こすから
腕に力を込めようとすると、その力は腕だけでなく、肩や背中、体幹といった他の筋肉にも連動して伝わります。この連動が、意図しない体のブレを引き起こします。
下半身でしっかりスタンスを固めていても、上半身が力みによって揺れてしまっては、ダーツの発射台そのものが安定しません。結果として、ダーツは狙った場所から大きく外れてしまいます。
3. 腕の可動域が狭くなり、しなやかさが失われるから
筋肉は、力を入れると硬直し、動かせる範囲(可動域)が狭くなります。リラックスした状態であれば腕はしなやかにムチのように振れますが、力が入ると関節の動きが硬くなり、スムーズな腕の振りができなくなります。
特に、リリースという繊細な動作が求められる場面で腕が硬直していると、ダーツを自然に離すことができず、引っかかってしまったり、押し出すような不自然な投げ方になったりします。
これらの理由から、ダーツは力でねじ伏せるスポーツではなく、不要な力みを取り除き、動作の再現性を高めるスポーツであると理解することが、上達への第一歩となります。
あわせて読みたい
「力は抜けているはずなのに、なぜか狙った場所に飛ばない」と感じる場合、原因は力みではなく「目線」や「身体構造のズレ」にあるかもしれません。以下の記事では、力み以外の物理的な原因を特定し、狙い通りに修正する方法を徹底解説しています。
上手い人はなぜ力んでいない?共通するフォームの特徴
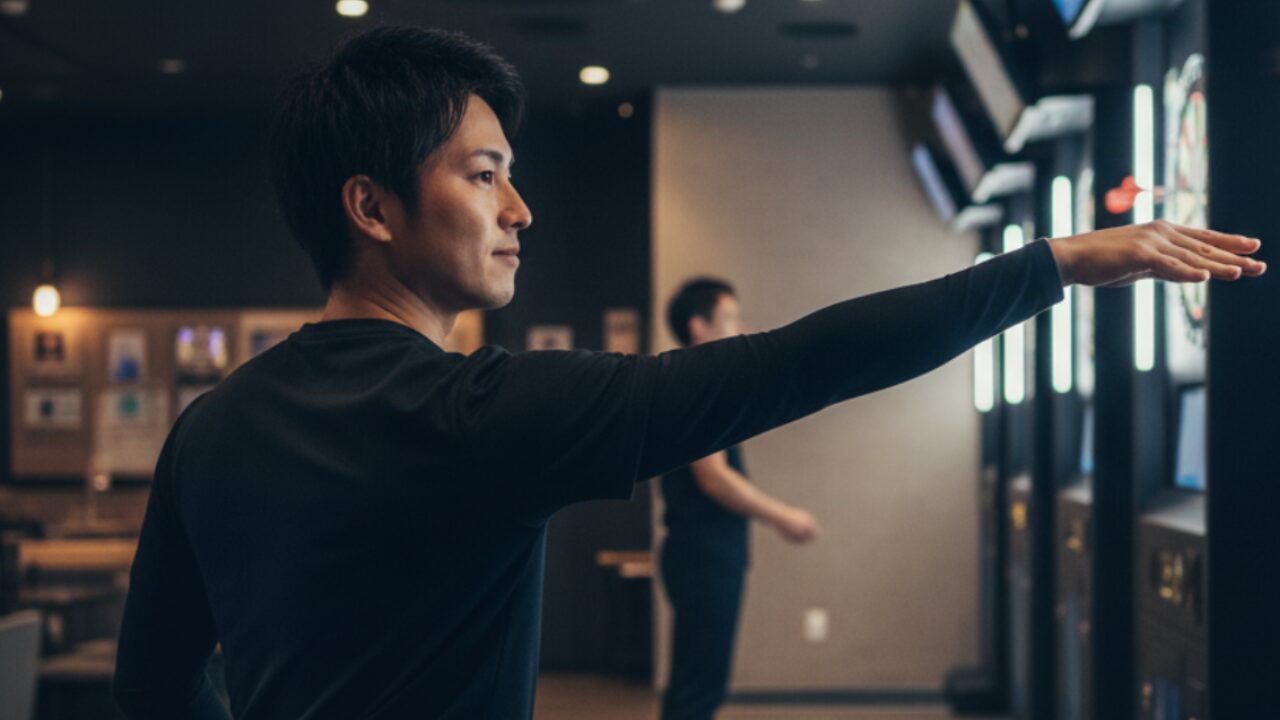
ダーツが上手い人やプロ選手のフォームを見ると、非常に滑らかで力みを感じさせません。彼らが力まないのには、明確な理由と、それに伴う共通の特徴があります。
結論から言うと、上手い人は「ダーツは腕力で投げるのではなく、物理法則を利用して飛ばすものだ」と理解しているからです。彼らは、ダーツの重さと腕の振りが生み出す遠心力を最大限に活用し、最小限のエネルギーでダーツを的に到達させる技術を持っています。
この考え方に基づいたフォームには、以下のような特徴が見られます。
| 特徴 | 解説 |
|---|---|
| リズムが一定 | セットアップからフォロースルーまでの一連の動作が、常に同じテンポで繰り返されます。力みはリズムを乱す原因となるため、安定したリズムは脱力ができている証拠です。 |
| フォロースルーが大きい | 投げ終わった後、腕が自然にターゲットに向かって伸びきっています。これは、腕の振りを途中で無理に止めることなく、エネルギーを完全にダーツに伝えきれていることを示します。力が入っていると、腕の振りにブレーキがかかり、フォロースルーが小さくなります。 |
| 下半身が揺るがない | 前述の通り、上半身の力みは体のブレに繋がります。上手いプレイヤーは上半身がリラックスしているため、下半身はどっしりと安定しており、3本投げ終わるまで軸が全くブレません。 |
また、精神面も大きく影響します。上手い人は、一本一本の結果に一喜一憂せず、常に平常心を保つメンタルの強さを持っています。過度な緊張や「絶対に入れなければ」というプレッシャーは力みの原因になりますが、彼らは対人戦の経験を積むことで、プレッシャー下でもリラックスした状態を保つ術を心得ています。
上手い人のフォームを真似る際は、形だけを模倣するのではなく、「なぜその動きをしているのか」「どうすればあんなに楽に飛ばせるのか」という、力みのなさに繋がる根本的な原理を考えることが上達への近道です。
腕の重さだけで飛ばす「正しい力の伝え方」とは

ダーツにおける「正しい力の伝え方」とは、筋力に頼るのではなく、腕そのものの重さを利用してダーツを振り子のように加速させることを指します。
この感覚を掴むための最も有名な例えが「紙飛行機を飛ばすイメージ」です。紙飛行機を遠くに綺麗に飛ばしたい時、力任せに投げると失速してすぐに落ちてしまいます。むしろ、そっと腕を振って最適な角度でリリースしてあげた方が、スムーズに遠くまで飛んでいきます。ダーツもこれと全く同じ原理です。
この技術の核となるのが、「ゼロポジション」という考え方です。ゼロポジションとは、重力に逆らって腕を上げた際に、最も筋肉を使わずに楽に腕を静止できる位置を指します。
多くの人にとっては、肘を基点に腕がL字になるあたりがそれに該当します。この最もリラックスした状態を基準点とすることで、不要な力みを排除したスイングが可能になります。
ゼロポジションを起点とした力の伝え方
- スタンスを決め、リラックスして立つ。
- 腕を上げ、筋肉が最も楽な「ゼロポジション」で構える。この時、ダーツを強く握らず、指の上に乗せているだけの感覚を持つ。
- テイクバックでは、腕を「引く」のではなく、重力に従って腕が自然に「倒れる」のを待つイメージ。
- そこから、倒れた腕が振り子のように前に戻る力を利用して、腕をターゲットに向かって伸ばしていく。
- リリースは、指で「離す」のではなく、腕が伸びきる過程でダーツが自然に指から「抜けていく」感覚。
重要なのは、一連の動作の中で「力を加える」意識を捨てることです。力は、ダーツを支え、腕を上げるための最低限のもので十分です。あとは腕の重さと振り子運動が、ダーツを的まで運んでくれます。この感覚が身につけば、長時間投げても疲れにくく、再現性の高いスローが手に入ります。
グリッププレッシャーを確認する簡単なセルフチェック方法

脱力したスローを実現するためには、グリップ、つまりダーツの握り方が非常に重要です。多くの人が無意識のうちにダーツを強く握りすぎており、それがリリースミスや力みの原因となっています。自分が適切な力で握れているかを確認するための簡単なセルフチェック方法を紹介します。
理想的なグリッププレッシャーは、「ダーツの重さを指で感じられるが、ダーツがぐらつかないギリギリの力加減」です。これを確かめるには、以下のステップを試してみてください。
ステップ1:フェザータッチで持ってみる
まず、羽に触れるかのように、全く力を使わずにダーツを指の上に乗せてみます。おそらく、この状態ではテイクバックの際にダーツが指の上で動いてしまい、安定しないはずです。これがグリッププレッシャー「0」の状態です。
ステップ2:少しずつ力を加えていく
次に、ステップ1の状態から、ダーツがぐらつかなくなるまで、ほんの少しずつ指に力を加えていきます。テイクバックで腕を引いてもダーツの先端がブレなくなった点が、あなたにとっての「最低限必要なグリッププレッシャー」です。
このチェックは、練習の最初(アップ)の段階で毎回行うことをお勧めします。その日の体調によっても最適な力加減は微妙に変わるため、常に自分の「基準」を確認する癖をつけることが大切です。
こんな症状は握りすぎのサイン
- リリースしたダーツが、狙った場所より下に落ちることが多い(指が引っかかっている証拠)。
- 指先にダーツの刻み(カット)の跡がくっきりと残る。
- 投げ終わった後、指がこわばっている感じがする。
これらの症状に心当たりがある場合、現在感じているよりも、もっと力を抜いて握ることを意識してみてください。ダーツは「握る」のではなく「支える」という感覚を持つことが、脱力への重要な一歩となります。
構えの瞬間から力が入る「セットアップ力み」の解消法

スローラインに立ち、ダーツを構える「セットアップ」の段階から既に肩や腕に力が入ってしまう、いわゆる「セットアップ力み」。これは、的を意識しすぎるあまり、「これから投げるぞ」と体が過剰に準備してしまうことで起こります。
この問題を解消するための有効なアプローチが、「ノーセットアップ」を試してみることです。ノーセットアップとは、その名の通り、顔の前などでダーツを静止させる「構え」の時間を意図的になくし、腕の流れの中で投げる方法です。
ノーセットアップのやり方と効果
やり方はシンプルで、スローラインに立ったら、構えて静止する時間を取らず、腕を上げる動作からテイクバック、そしてスローまでを一つの流れるような動作として行います。静止するポイントがないため、力が入る「きっかけ」そのものを排除することができます。
この練習には、以下のような効果が期待できます。
- 腕の重みを感じやすい: 腕を常に動かしているため、腕そのものの重さを感じやすく、その重さを利用して投げる感覚を掴むきっかけになります。
- リズムが生まれる: 動作を止めないことで、自分なりの心地よいスイングリズムが生まれやすくなります。
- 精神的なプレッシャーの軽減: 構えて狙う時間が短い分、「外したらどうしよう」といった雑念が入りにくくなります。
もちろん、最終的にノーセットアップを自分の正式なフォームにする必要はありません。あくまでセットアップで力んでしまう原因を探り、「力を入れなくてもダーツは投げられる」という感覚を体に覚えさせるための練習ドリルとして捉えることが重要です。
セットアップで力みを感じる方は、一度この練習を取り入れてみてください。静止した状態から投げることだけがダーツではないと知ることで、心身ともにリラックスするヒントが見つかるはずです。
テイクバックで「腕が固まる」原因と肘を柔らかく使う意識

ダーツを引く動作である「テイクバック」の最中や、引ききった最下点で腕がカチッと固まってしまい、スムーズに腕を前に出せなくなる症状。これは、ダーツの「イップス」と呼ばれる運動障害の一種として多くのプレイヤーを悩ませています。
この現象の主な原因は、身体的な問題と精神的な問題が複雑に絡み合っていることにあります。
身体的な原因:間違った運動学習
人間の脳は、反復練習によって特定の動作を「運動回路」として記憶します。しかし、フォームを過度に意識しすぎたり、無理な修正を繰り返したりすることで、脳が混乱し、異常な運動回路を形成してしまうことがあります。その結果、「腕を引いたら、一度止めてから、力を入れて押し出す」といった間違った動作が癖になってしまい、腕が固まるという症状として現れます。
精神的な原因:パフォーマンスへの不安
「ブルに入れたい」「外したくない」という強いプレッシャーや、過去の失敗体験(トラウマ)が、無意識に腕の動きにブレーキをかけてしまうことも大きな原因です。脳が「このまま投げたら失敗するかもしれない」と判断し、体を守るための防御反応として筋肉を硬直させてしまうのです。
腕が固まる症状が出た時に、「とりあえず投げ込んで治そう」とするのは逆効果です。異常な運動回路をさらに強化してしまう危険性があります。
改善へのアプローチ:肘を柔らかく使う意識
改善のためには、まず「肘を支点にする」というダーツの基本原理に立ち返ることが重要です。テイクバックは腕全体で「引く」のではなく、肘の位置を固定したまま、前腕が自然に後ろへ「倒れる」という意識を持ちます。そして、そこから腕を「出す」のではなく、倒れた前腕が振り子のように自然に「返ってくる」動きに任せます。
この時、肘関節をガチガチに固めるのではなく、あくまで柔らかく、蝶番(ちょうつがい)のように使うことを意識してください。この意識を持つことで、テイクバックからリリースまでの一連の動作がスムーズに繋がり、腕が途中で固まるという症状の緩和が期待できます。
実践的なダーツの脱力とコツ【応用編】

- 肩が上がってしまう人必見!肩の力みを抜く簡単ストレッチ
- 「脱力しすぎ」でダーツが飛ばない?最低限必要な力加減の見つけ方
- 指先でダーツを「擦って投げる」感覚を掴む練習法
- 自宅でできる!脱力フォームを体に覚えさせる効果的な練習法3選
- 「ブルに入れよう」と意識しすぎないメンタルの作り方
- フォロースルーで確認するダーツ脱力のコツ
肩が上がってしまう人必見!肩の力みを抜く簡単ストレッチ

ダーツを構えたり、投げたりする際に、無意識のうちに利き腕の肩が上がってしまうことがあります。これは典型的な力みのサインであり、肩周りの筋肉が硬直することで、腕の振りが窮屈になり、コントロールが安定しなくなります。
この問題を解消するためには、意識的に肩の力を抜くことが必要です。しかし、ただ「力を抜け」と言われても難しいものです。そこで有効なのが、投げる前や練習の合間に行う簡単なストレッチと、力みを防ぐための意識改革です。
投げる前にできる!肩回りの簡単ストレッチ
筋肉は一度収縮させてから弛緩させると、リラックスしやすくなる性質があります。これを利用したストレッチが効果的です。
- 両肩をぐっとすくめ、耳に近づけるように5秒間力を入れます。
- その後、ストンと一気に力を抜き、肩を落とします。
- この動作を2~3回繰り返します。
これだけで肩周りの筋肉の緊張がほぐれ、リラックスした状態を作りやすくなります。
意識するポイントをずらす
「肩を上げるな」と意識すればするほど、かえって肩に意識が集中し、力んでしまうことがあります。これは人間の体の面白いところで、特定の部位を意識すると、その部位の筋肉が緊張しやすくなるのです。
そこで、あえて肩以外の部分に意識を向けるというアプローチが非常に有効です。例えば、以下のようなことを考えてみてください。
- 足の裏の感覚に集中する: 「今は母指球に体重が乗っているな」など、足の裏に全神経を集中させます。
- 肘の高さを意識する: 肩ではなく、「肘が下がらないように」ということだけを考えます。
- 呼吸に意識を向ける: 投げる前にゆっくりと息を吐き、呼吸そのものに集中します。
意識を別の場所に向けることで、肩は「意識されない」状態になり、本来の自然な動きを取り戻しやすくなります。肩の力みに悩んでいる方は、ぜひこの「意識をずらす」テクニックを試してみてください。
「脱力しすぎ」でダーツが飛ばない?最低限必要な力加減の見つけ方

「脱力」を意識するあまり、今度は逆に力が抜けすぎてしまい、「ダーツがボードまで届かない」「矢が山なりになりすぎて狙えない」といった新たな問題に直面することがあります。これは「脱力」という言葉を「無力」と誤解していることから生じます。
ダーツにおける脱力とは、不要な力を取り除き、必要な力だけで投げることを意味します。では、その「最低限必要な力」とはどの程度のものなのでしょうか。
それは、「テイクバックの最下点でダーツの重さを支えきれ、ダーツがぐらつかない程度の力」です。
力が抜けすぎている状態では、腕を後ろに引いた際にダーツの重さに指が負けてしまい、ダーツの先端が下を向いたり、左右にブレたりします。この状態から投げても、ダーツに正しく力が伝わるはずがありません。
つまり、脱力とは言っても、グリップと、腕を構えた位置に保持するための力は当然必要になります。問題なのは、そこから腕を振る際に余計な力を加えてしまうことなのです。
最低限の力加減を見つける練習法
前述の通り、グリッププレッシャーのセルフチェックがここでも役立ちます。
- まずは羽に触るような「フェザータッチ」でダーツを持つ。
- その状態でゆっくりとテイクバックを行う。おそらくダーツはぐらつくはずです。
- そこから、テイクバックしてもダーツが安定するギリギリのポイントまで、ほんのわずかずつ握る力を強くしていく。
その「ギリギリのポイント」が、あなたにとっての最適な力加減の基準となります。それ以上の力は、すべて「力み」である可能性が高いです。
あわせて読みたい
脱力のコツが掴めたら、次はそれを「再現性のあるフォーム」として定着させる段階です。以下の記事では、フォーム固めに最適な練習メニューや、上達を助けるマイダーツの選び方を完全網羅しています。
指先でダーツを「擦って投げる」感覚を掴む練習法
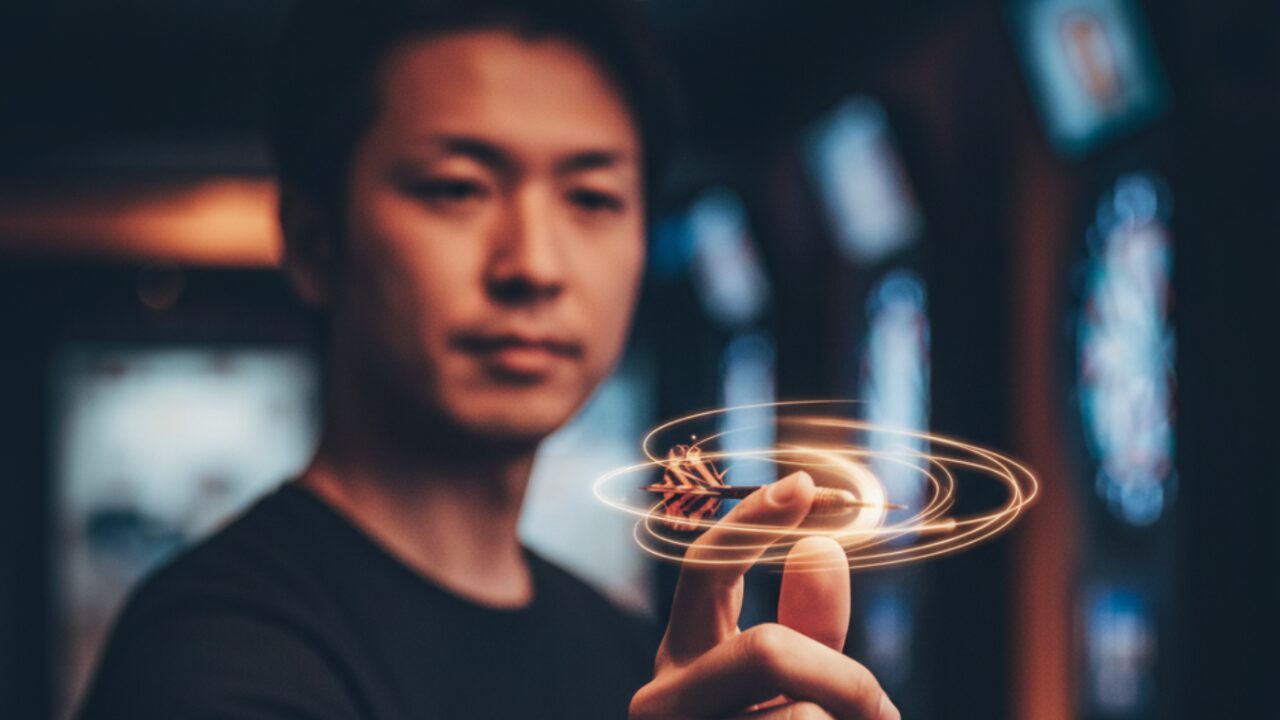
ダーツの投げ方には、大きく分けて「押し投げ」「抜き投げ」そして「擦り投げ」があると言われています。特に近年、トッププレイヤーの間で注目されているのが、リリースを非常にスムーズにする「擦って投げる」技術です。
「擦って投げる」とは、リリース(ダーツを離す瞬間)の際に、人差し指の腹でバレルの側面を軽く擦るようにして、ダーツに最後の回転と方向性を与える投げ方です。この投げ方ができると、手首や指に余計な力が入らず、ダーツが指から綺麗に抜けていくため、非常に安定した軌道を描きやすくなります。
「擦る感覚」を掴むためのポイント
この感覚を掴むためには、グリップの仕方が重要になります。ダーツを真上から鷲掴みにするのではなく、親指と中指でダーツを支え、人差し指はバレルの側面に軽く添えるようなグリップが基本となります。
そして、スローイングの過程で以下のことを意識します。
- テイクバックから腕を前に出す際に、親指でダーツを「押す」意識をなくす。
- 代わりに、腕が前に伸びていく遠心力でダーツが自然に飛んでいくのに任せる。
- ダーツが指から離れる最後の瞬間に、バレルの側面を人差し指の腹が「撫でる」または「軽く触れる」のを感じる。
この時、無理に擦ろうとしたり、回転をかけようとしたりする必要はありません。正しいグリップと脱力ができていれば、腕を振るだけで自然に指がダーツの側面を擦る形になります。
最近では、この「擦り投げ」がしやすいように設計されたダーツバレルも多く販売されています。バレルの側面に特徴的なカットが入っているものや、人差し指がフィットしやすい形状のものがそれに当たります。道具の補助を得るのも、感覚を掴むための一つの有効な手段です。
「押し出す」感覚から抜け出せない方や、リリースでダーツが引っかかる感じがする方は、この「擦って投げる」意識を取り入れてみると、ブレイクスルーのきっかけになるかもしれません。
自宅でできる!脱力フォームを体に覚えさせる効果的な練習法3選

ダーツの脱力フォームを習得するには、ダーツボードに向かってひたすら投げ込むだけが練習ではありません。むしろ、スコアを気にせずに行える自宅での地道な反復練習こそが、体に正しい動きを染み込ませる一番の近道です。
ここでは、ダーツボードがなくてもできる、効果的な練習法を3つ紹介します。
1. 紙飛行機を飛ばす
これは、脱力して投げる感覚を最も簡単に理解できる練習法です。実際に紙飛行機を折って、それを部屋の向こう側にある目標(例えばゴミ箱など)に向かって飛ばしてみてください。
力いっぱい投げると紙飛行機は失速し、コントロールも定まりません。しかし、そっと腕を振り、最適な角度でリリースしてあげると、驚くほどスムーズに飛んでいきます。この「そっと押し出す」「軌道に乗せてあげる」という感覚こそ、ダーツの脱力スローの神髄です。
2. タオルを使ったシャドースイング
フェイスタオル程度の大きさのタオルを用意し、その端を持ちます。そして、実際にダーツを投げるのと同じように腕を振ってみてください。腕に力が入っていると、タオルは綺麗に振れず、硬い動きになります。
一方、肩や肘をリラックスさせ、腕全体をしなやかなムチのように使うことができると、タオルの先端は「ヒュッ」と綺麗な音を立てて走ります。この練習は、腕の力を抜き、スイングスピードを上げる感覚を養うのに最適です。
3. 鏡の前でのフォームチェック
全身が映る鏡の前に立ち、自分のフォームを確認しながらゆっくりと素振りを行います。この練習の目的は、自分のイメージしている動きと、実際の動きのズレを発見することです。
チェックポイント
- 肘の高さは毎回同じか?
- テイクバックで肩が上がっていないか?
- 投げ終わった後、腕はまっすぐターゲットの方向を向いているか?
- 体全体が前後に揺れていないか?
スマートフォンで自分のフォームを撮影し、スローモーションで確認するのも非常に効果的です。客観的に自分の姿を見ることで、自分では気づかなかった力みの原因や癖を発見できます。
「ブルに入れよう」と意識しすぎないメンタルの作り方

ダーツの力みは、技術的な問題だけでなく、精神的なプレッシャーに起因することも非常に多いです。「ブルに入れなければ」「この一本を外せない」といった強い意識が、無意識のうちに体を硬直させてしまいます。
これは心理学的苦悩からくるイップスの一種とも言え、特に真面目に練習する人ほど陥りやすい罠です。この問題を克服するためには、技術練習と並行して、意識をコントロールするメンタルのトレーニングが必要になります。
目標設定を細分化する
多くの場合、プレッシャーは目標設定が高すぎることによって生じます。「ブルに入れる」という最終結果だけを目標にすると、一本外すごとに「失敗した」というネガティブな感情が蓄積します。そこで、目標をもっと手前の、達成しやすいものに設定し直すことが有効です。
目標設定の例
- 「ブルに入れる」→「まずはボードに届かせる」
- 「3本とも同じ場所に集める」→「まずは1本、気持ちよく腕を振ることに集中する」
- 「クリケットで相手より先に陣地を埋める」→「まずはS20に1本入れることだけを考える」
大きな目標を、達成可能な小さなステップに分解することで、「成功体験」を積み重ねやすくなります。小さな成功は自信に繋がり、自信は心の余裕を生み、結果として体の力みが抜けていくという好循環が生まれます。
結果ではなくプロセスを評価する
ダーツがブルに入ったか入らなかったか、という「結果」だけで自分のスローを評価するのをやめてみましょう。代わりに、「プロセス」、つまり投げ方そのものが良かったかどうかを評価の基準にします。
たとえブルを外したとしても、「今のスローは力みがなく、スムーズに腕が振れたな」と感じられたなら、それは「良いスロー」だったと自分を肯定してあげることが大切です。逆に、偶然ブルに入ったとしても、力任せの投げ方だったのであれば、それは改善すべきスローです。
結果は後からついてくるものです。まずは一本一本、自分の理想とするプロセスで投げられたかどうか。そこに集中することで、結果に対する過剰なプレッシャーから解放され、心身ともにリラックスした状態に近づくことができます。
フォロースルーで確認するダーツ脱力のコツ

ダーツの脱力が正しくできているかどうかは、投げ終わった後の腕の形、つまり「フォロースルー」に最も顕著に現れます。フォロースルーは、単なる投げ終わりのポーズではなく、自分のスローがどうであったかを教えてくれる重要なバロメーターです。
理想的なフォロースルーは、「投げたダーツの軌道を追いかけるように、腕がターゲットに向かって自然に伸びきっている状態」です。この形になっていれば、腕の振りのエネルギーがスムーズにダーツに伝わり、途中で力によるブレーキがかかっていない証拠となります。
ここでは、自分のフォロースルーをセルフチェックするためのポイントをまとめます。
- ダーツは送り出すという意識を持つ
- 力みは再現性を下げ、体のブレを生む
- 上手い人は腕力ではなく物理法則でダーツを飛ばす
- 脱力ができているとリズムが一定でフォロースルーが大きい
- 正しい力の伝え方は腕の重さを利用した振り子運動
- 構えは最も楽な位置「ゼロポジション」を見つける
- グリップはダーツを「支える」だけで強く握らない
- セットアップで力むなら「ノーセットアップ」を試す
- 腕が固まるのは精神的なプレッシャーも大きな原因
- 肩の力みはストレッチや意識をずらすことで解消する
- 脱力しすぎもNG、ダーツを支える最低限の力は必要
- 擦って投げる技術はスムーズなリリースを助ける
- 自宅でのタオル振りや鏡での素振りは効果的
- 目標を細分化し、結果よりプロセスを重視する
- フォロースルーが綺麗に伸びれば脱力ができている証拠
