
ダーツを始めたばかりの方や、ルールや用語に詳しくなりたいと考えている方にとって、「ダーツのホワイトホースと は」といったキーワードで調べるのは、ごく自然な流れです。ホワイトホースとは、ダーツの中でも特にクリケットというルールで登場する、達成が極めて難しいアワードの一つです。その意味や由来、発生条件を知ることで、プレイ中の戦略がより深まるでしょう。
本記事では、ホワイトホースの難易度や評価、達成に必要なスキルに加え、ブルに3本入れた場合の名前や、オーバーキルの意味、バーストの仕組みといった重要ルールもわかりやすく解説していきます。また、初心者向けの用語集や、スティールダーツとソフトダーツの違い、大会で気をつけたい暗黙のルールにも触れています。
さらには、スタッツで注目すべき指標、ダーツの遊び方やゲームの種類、スランプの解消法など、あらゆる角度からダーツの奥深さを紹介していきます。これからダーツを本格的に楽しみたい方や、中級者を目指す初心者にとって、実践的なガイドとなる内容です。
記事のポイント
- ホワイトホースの意味や由来を理解できる
- クリケットルールにおける達成条件がわかる
- 難易度や戦術面でのポイントを学べる
- ダーツ全体に関する基礎知識を広く把握できる
ダーツのホワイトホースと は?意味や由来を解説

- ホワイトホースの意味と由来
- ホワイトホースが登場するクリケットのルール
- ホワイトホースの難易度はどれくらい?
- ダーツでブルに3本入れると何と呼ばれる?
- ダーツのスタッツで注目すべき指標
- 初心者が覚えておきたいダーツ用語集
ホワイトホースの意味と由来
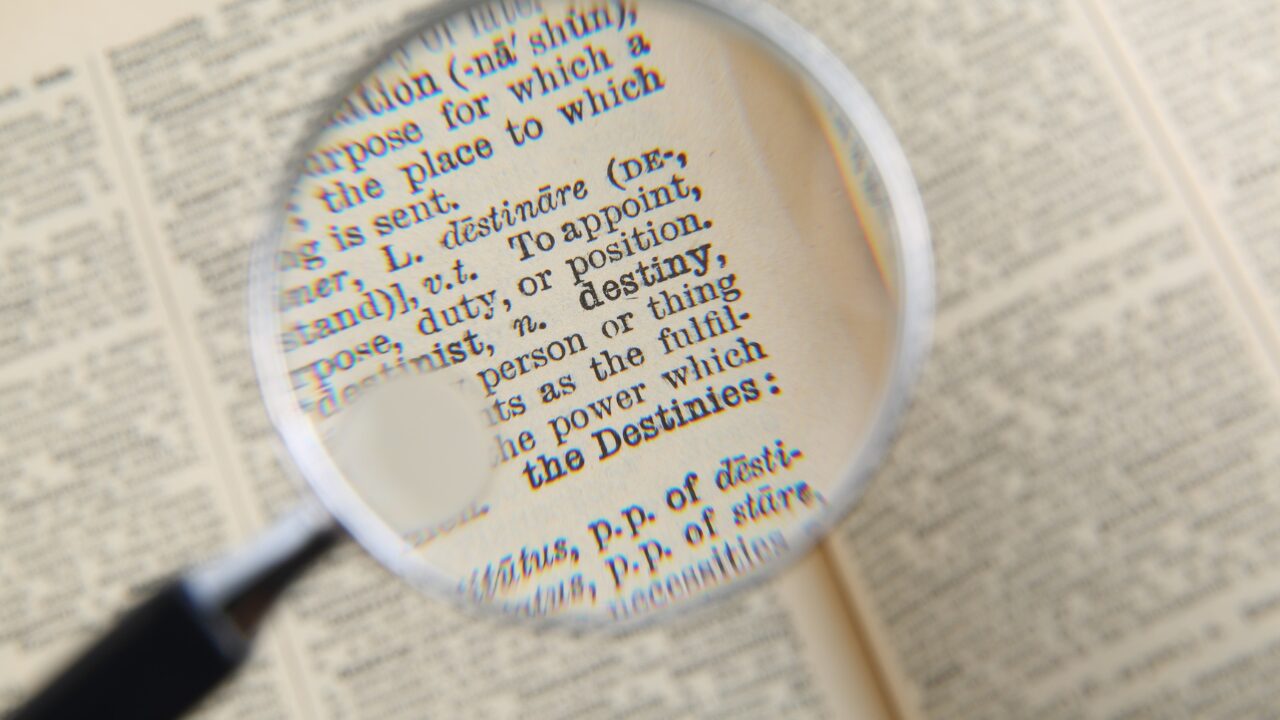
ホワイトホースとは、ダーツのクリケットというゲームで達成できる特別なアワードの一つです。1ラウンド中に、異なる3つのクリケットナンバー(20〜15)のすべてトリプルエリアに命中させると獲得できます。
これは非常に難易度が高く、複数のプロダーツプレイヤーであっても頻繁に出せるものではありません。クリケットにおけるアワードの中でも、ホワイトホースは「最難関」と言われています。
名前の由来については複数の説がありますが、よく知られているのはメリーゴーランド説です。ターゲットを順に切り替えて狙うプレイスタイルが、回転するメリーゴーランドの白馬を連想させることから、「ホワイトホース」と呼ばれるようになったという説です。
また、別の由来として「ホワイトホース・ラピッド(白馬の急流)」という地名に由来するという説もあります。これは、急流の白波が白馬のたてがみに似ていたことから名付けられた地名で、そのインパクトから転じてこのアワード名になったという考え方です。
どちらの説にせよ、ホワイトホースという名称は、美しくも難易度の高いプレイを象徴するのにふさわしいものです。ちなみに、ダーツマシンの演出でも白馬が走る映像が流れることがあり、その演出も含めて注目されるアワードとなっています。
ホワイトホースが登場するクリケットのルール

ホワイトホースは、ダーツのゲーム形式「クリケット」においてのみ登場するアワードです。クリケットは、15〜20のナンバーとブル(中心)を使って、点数を競いながら相手より先に数字を「クローズ(閉じる)」するルールが特徴です。
このゲームにおいてホワイトホースは、1ラウンド内で3本すべてを異なるクリケットナンバーのトリプルエリアに命中させることによって発生します。例えば「T20・T19・T18」のように、それぞれ異なる数字のトリプルに1本ずつ命中させる必要があります。
同じナンバーに複数本入れてもホワイトホースにはなりません。例えば「T20・T20・T19」では条件を満たさず、ただの9マーク扱いになります。また、トリプルに命中していても、すでにクローズされているナンバーであればスコアとしてカウントされず、ホワイトホースも認定されない場合があります。
このため、ホワイトホースは技術だけでなく、狙うタイミングや戦況を見極める判断力も求められるのが特徴です。狙えるチャンスが少ないことから、非常にレアなプレイとしてプレイヤー間でも特別視されています。
一度でも達成すれば、試合の流れを一気に変える可能性もあるほど影響力があり、クリケットを極めたい人にとってはひとつの目標とも言えるアワードです。
ホワイトホースの難易度はどれくらい?

ホワイトホースは、ダーツの中でも特に難易度が高いアワードのひとつとされています。ダーツ経験者であっても簡単には達成できず、長年プレイしている人でも一度も出したことがないというケースも珍しくありません。
このアワードが難しいとされる最大の理由は、異なる3つのクリケットナンバーすべてに、1ラウンド内でそれぞれ1本ずつトリプルで命中させなければならないことです。例えば、T20・T19・T18といった3つの異なるターゲットを連続して正確に狙う必要があります。
トリプルリングは面積が小さく、狙うには高い集中力と安定した技術が不可欠です。さらに、ターゲットが上下にバラついているため、エイミング(照準合わせ)とフォームの切り替えも求められます。特にT20からT18に移動するようなパターンでは、わずかなズレが命取りとなります。
加えて、プレイ中にホワイトホースを狙える状況自体が少ないという現実もあります。クリケットでは戦略的に数字をクローズしたり点数を稼ぐことが優先されるため、ホワイトホースを意識して投げられるタイミングは限定されるのです。
このような背景を踏まえると、ホワイトホースは単なる技術だけでなく、実力・集中力・戦略判断のすべてが求められるアワードだと言えるでしょう。
ダーツでブルに3本入れると何と呼ばれる?

ダーツで1ラウンド内に3本すべての矢を「ブル」に命中させると、それは**「ハットトリック」**と呼ばれるアワードになります。ブルとは、ダーツボード中央の得点エリアで、一般的には「インブル(50点)」と「アウターブル(25点)」の2種類が存在します。
3本すべてがインブル(内側の中央)に命中した場合は、さらに上位のアワードである**「スリー・イン・ザ・ブラック」**と呼ばれ、ハットトリックよりも難易度が高いとされています。特にスリー・イン・ザ・ブラックは、視認性が高く、観戦者からも注目される場面です。
ブルに安定して入れるためには、狙いの正確さはもちろん、力加減やリリースのタイミングなど、細かなテクニックが求められます。そのため、初心者にとってはブルに1本でも入れることが目標になりがちですが、3本すべて命中させるには相当な練習が必要です。
一方で、ブル系アワードは得点力だけでなく、プレッシャーのかかる場面での集中力を示すものでもあります。特に01ゲームのフィニッシュにおいて、ブルの精度は勝敗を大きく左右する要素です。
つまり、ハットトリックやスリー・イン・ザ・ブラックは、得点・集中力・安定感を兼ね備えたプレイヤーの証明とも言えるアワードです。
ダーツのスタッツで注目すべき指標

ダーツにおける「スタッツ」とは、プレイヤーの実力を数値で表すための統計データのことです。スタッツは上達度を把握するための重要な指標であり、定期的に確認することで自身の成長や課題を明確にすることができます。
中でも注目すべきスタッツは、主に「PPD」と「MPR」の2つです。PPD(Points Per Dart)は01ゲームにおける1投あたりの平均得点を示し、特にソフトダーツでよく用いられます。例えば、1ラウンドで60点を取った場合、PPDは「20」となります。この数値が高いほど、得点力に優れていることを意味します。
一方で、クリケットゲームでは「MPR(Marks Per Round)」が重要です。これは1ラウンドあたりにどれだけ有効なマークを付けたかを数値化したもので、クリケット特有の戦術的な実力を評価する指標です。例えば、MPRが3.0を超えると中級者以上の実力と判断されることもあります。
他にも、「勝率」「アレンジ率」「1ラウンド平均」などの細かなスタッツも存在しますが、初心者や中級者がまず注目すべきなのはPPDとMPRです。これらを把握することで、自分の強みや弱点を数値で理解できるようになり、効率的な練習にもつながります。
いずれにしても、スタッツは「結果」ではなく「経過」の記録です。上達のペースは人それぞれなので、過度に一喜一憂せず、継続して記録を見ながら改善していくことが大切です。
初心者が覚えておきたいダーツ用語集
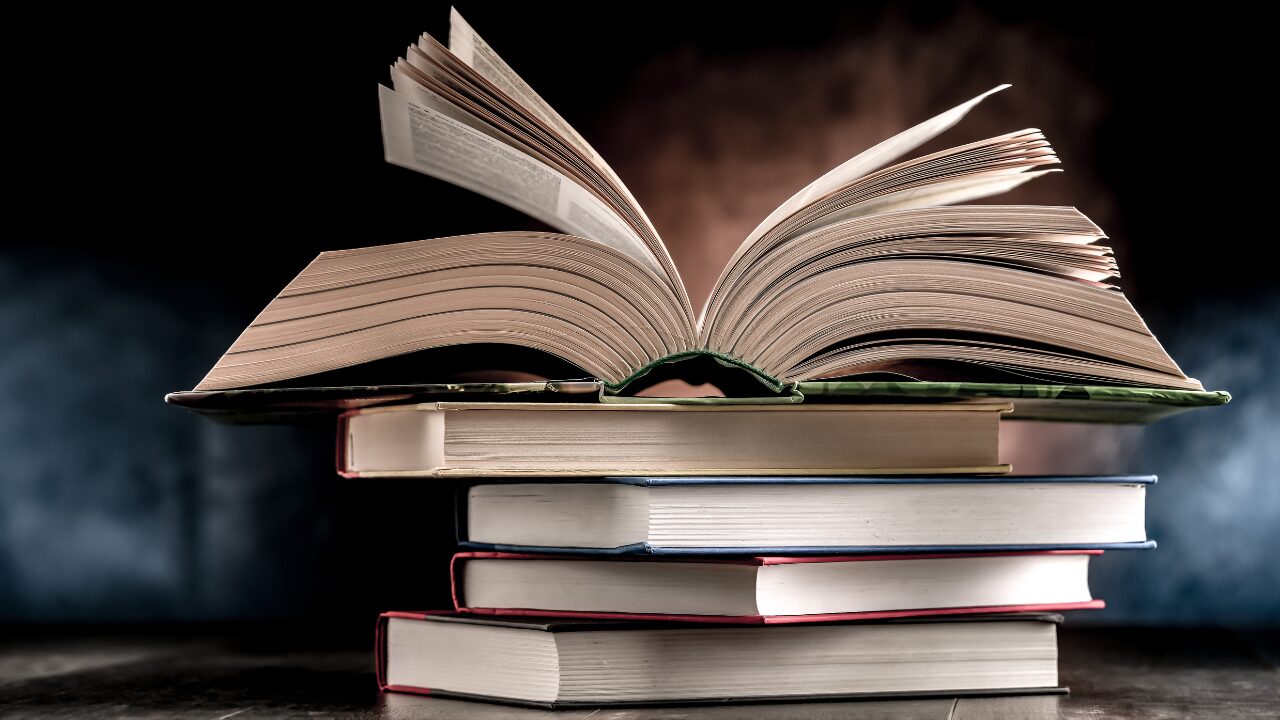
ダーツを始めたばかりの方にとって、専門用語の多さは障壁になりがちです。用語を正しく理解することで、ルールや戦術をスムーズに習得でき、ゲームをより楽しめるようになります。
まず覚えておきたいのが「ブル」と「トリプル」です。ブルはダーツボードの中心にあるエリアで、内側が50点(インブル)、外側が25点(アウターブル)です。トリプルは各ナンバーの細い内側リングで、その数字の3倍の点数になります。例えば、T20(トリプル20)は60点です。
続いて、「クローズ」「プッシュ」「カット」などはクリケットで頻出の用語です。クローズはナンバーを3回ヒットさせて得点対象から外す行為を指し、プッシュは自分がすでにクローズしたナンバーで追加得点を狙うプレイです。カットは、相手が得点を狙っているナンバーを先にクローズして封じる戦術です。
その他にも、「アワード(特定の好プレイに与えられる演出)」「スタッツ(成績の統計値)」「スローライン(ダーツを投げるライン)」なども、よく耳にする言葉です。
これらの用語を理解しておくと、ルール説明を受けたときや試合を観戦するときにも混乱せずに済みます。ダーツに慣れてくると自然と使いこなせるようになりますが、最初は簡単なメモや用語集を手元に置いておくと便利です。
ダーツのホワイトホースと は攻略可能か?戦術と対策を紹介

- ダーツにおけるオーバーキルとは
- ダーツの「バースト」の仕組みと対処法
- ダーツ大会でのマナーと暗黙のルール
- ダーツのスランプを抜け出すには?
- スティールダーツとソフトダーツの違い
- ダーツの遊び方とゲームの種類まとめ
ダーツにおけるオーバーキルとは

オーバーキルとは、ダーツの「クリケット」ルールにおいて、相手との得点差が200点以上開いている状態で加点を続けてしまうプレイのことです。この状況では加点が無効になる仕様が多く、ルール上は成立していてもマナー面での議論を呼びやすい特徴があります。
クリケットでは、得点できるナンバー(15〜20とブル)をお互いに「クローズ」していく形式です。通常、クローズが終わっていないナンバーで得点を重ねることは有効な戦術ですが、点差が大きく開きすぎると、一方的な展開になってしまい、対戦相手に精神的なプレッシャーや不快感を与えることがあります。これが「マナー違反」とされる所以です。
実際には、200点差を超えるとシステム上で加点が無効になる設定のマシンもあります。ただし、すべての環境でこの制限があるわけではなく、プレイヤー側が気をつけるべきポイントです。
また、うっかりオーバーキルになる場合も少なくありません。たとえば、点差の確認を怠っていたり、カウントの意図が伝わっていなかったりすると、結果的に過剰な加点になってしまいます。
重要なのは、ゲームを楽しむためには相手へのリスペクトを忘れないことです。戦略的な加点と、相手の士気を削ぐ行為の境界線を理解し、状況に応じた判断を心がけましょう。
ダーツの「バースト」の仕組みと対処法

バーストとは、主に「01ゲーム」で発生する現象で、目標スコアのぴったりに達しなかった場合や、得点がオーバーしてしまった場合に、そのラウンドの得点が無効になるルールのことです。簡単に言えば、ゼロにするための計算や調整に失敗すると、得点が「なかったこと」になる仕組みです。
たとえば、残り点数が32点のときに、ダブル16に命中すれば勝利ですが、誤ってシングル16に当たると残りが16点になり、次のダーツでシングル16を再び狙っても32点を超えてしまい、結果的にバーストとなります。つまり、計算ミスや狙いのズレによって、ラウンド全体が無効になる可能性があるのです。
このルールの存在は、戦略性を高めると同時に、終盤の緊張感を生み出します。特に初心者のうちは、狙うべき場所や残り点数の調整が難しく、バーストを繰り返してしまうことも珍しくありません。
対処法としては、まず「アウトチャート」を覚えることが有効です。アウトチャートとは、残り点数ごとに最適な狙いどころをまとめた表のことで、あらかじめ覚えておけば迷わずにプレイできます。また、ダブルを狙う精度が安定しないうちは、無理に攻めず安全策を取るのも一つの選択肢です。
バーストを避けるには、点数管理と冷静な判断力が不可欠です。焦らず、次に繋げるプレイを意識することで、勝率の安定にもつながっていくでしょう。
ダーツ大会でのマナーと暗黙のルール

ダーツ大会に参加する際は、ルールだけでなくマナーや暗黙の了解にも注意が必要です。これらは明文化されていないことが多いため、事前に知っておくことでトラブルを避け、円滑なプレイが可能になります。
まず大前提として、相手がプレイしている最中は視界に入らない場所で静かに待つことがマナーです。相手の背後で動いたり、声を出したりすると集中を乱す原因となります。また、1投目や2投目に対して「ナイス!」などと声をかけるのは一見好意的に思えますが、人によってはプレッシャーに感じることもあるため注意が必要です。
もう一つ重要なのが「他人のダーツを勝手に触らない」ことです。ダーツは個人の道具であり、グリップの質感やバランスなどにこだわりを持っているプレイヤーが多くいます。興味がある場合は、必ず本人の許可を取ってから触れるようにしましょう。
また、試合に勝っても過度にはしゃぐのは控えるべきです。感情表現が激しいと、相手に対して失礼と取られることがあります。逆に負けた場合も、投げやりな態度を見せるのではなく、礼儀正しく振る舞うことで大会全体の雰囲気が良くなります。
このような暗黙のルールは、会場の空気やプレイヤー同士の信頼関係を築くためにも大切です。初心者のうちは周囲の動きを観察しながら、自然に覚えていく姿勢を心がけましょう。
ダーツのスランプを抜け出すには?

ダーツを続けていると、突然調子が落ちて思うように投げられなくなる「スランプ」に陥ることがあります。これは珍しいことではなく、多くのプレイヤーが経験する過程のひとつです。
スランプの原因はさまざまですが、よくあるのは「フォームの迷い」「力の入れすぎ」「結果にこだわりすぎる意識」の3点です。自分の投げ方に自信がなくなり、無意識に崩れてしまうことが多く見られます。
まず取り組みたいのは、フォームの見直しです。過去に好調だったときの動画があれば、それを確認しながら再現してみると改善の糸口が見えてきます。また、調子を戻そうと焦るあまり、無理に力を入れてしまうことも逆効果です。特にリリース時の脱力を意識すると、投げやすさが戻ってくることがあります。
次に、結果よりも動作に集中することがポイントです。1本ごとの成否ではなく、自分のルーティンや腕の振りの感覚を重視することで、自然な投げ方を取り戻しやすくなります。
さらに、まったく別の練習メニューを取り入れるのも効果的です。たとえば、ゲーム形式を変える、狙うエリアをいつもと違う番号にする、練習時間を短く区切るなど、刺激を加えることで気分転換になります。
何よりも重要なのは、焦らず継続することです。スランプは一時的な停滞にすぎず、乗り越えれば確実に次のステップへ進めます。悩みすぎず、楽しむ気持ちを忘れずに取り組みましょう。
あわせて読みたい
スランプ脱出の鍵は、意外と「基礎の再確認」にあるかもしれません。迷いが生じたフォームをリセットし、着実に調子を取り戻すための「正しい練習手順」を以下の記事で詳しく解説しています。
スティールダーツとソフトダーツの違い
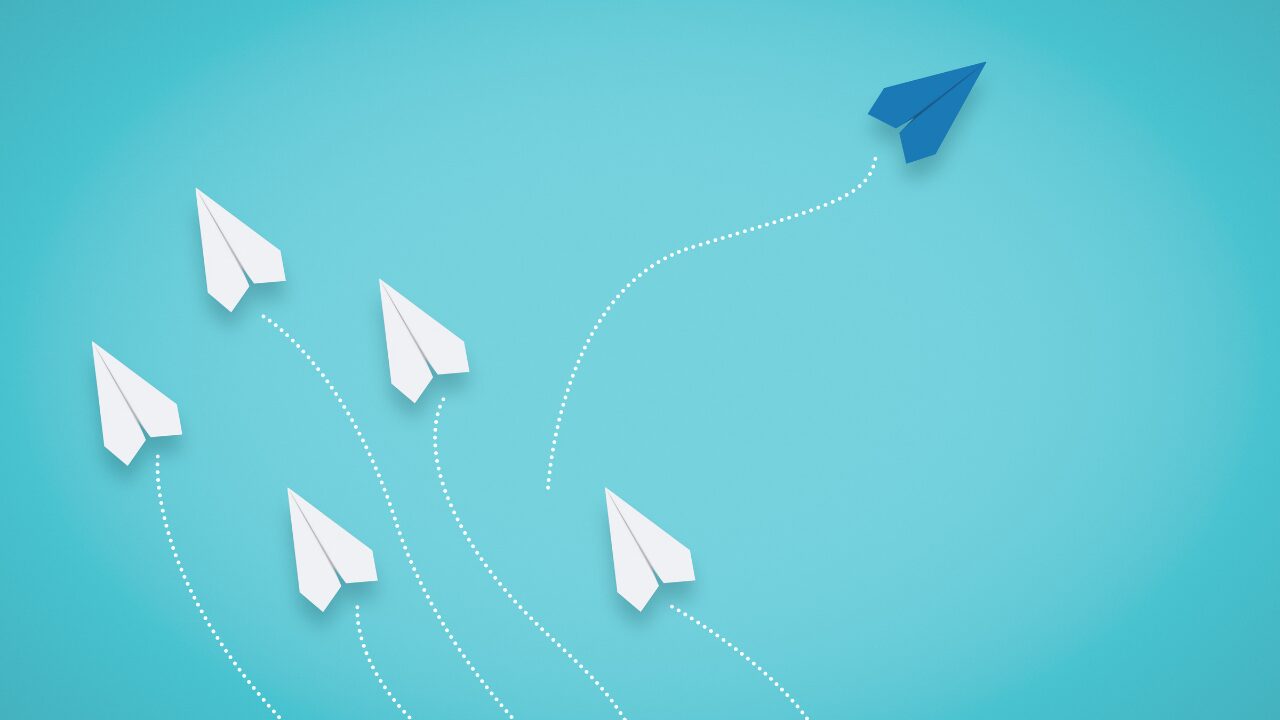
ダーツには大きく分けて「スティールダーツ」と「ソフトダーツ」の2種類があり、それぞれにルールや設備、プレイスタイルに違いがあります。どちらを選ぶかによって、使用する道具や競技の雰囲気も変わるため、まずは基本的な違いを把握しておきましょう。
スティールダーツは、先端が金属(スチール)製のダーツを使い、**ブリッスルボード(麻などで作られた硬いボード)**に投げる競技です。手動でスコアを計算することが多く、静かな環境でプレイされることが多いのが特徴です。プロのトーナメントや海外の大会ではスティールダーツが主流となっています。
一方でソフトダーツは、先端がプラスチック製の柔らかいダーツを使用し、電子式のボードに向かって投げる形式です。スコアが自動で表示されるため初心者にも扱いやすく、日本では主にダーツバーやアミューズメント施設で普及しています。音や光の演出もあり、カジュアルに楽しみたい人に向いています。
また、スティールダーツはダブルでフィニッシュしなければならないなど、ルールがやや複雑な場面もありますが、その分競技性が高いです。一方ソフトダーツはルールが簡潔で、気軽に始めやすいのが魅力です。
選ぶ基準は、プレイ環境や目的によって変わります。本格的に競技としてダーツを極めたいならスティールダーツ、まずは楽しみながら始めたい人にはソフトダーツがおすすめです。
ダーツの遊び方とゲームの種類まとめ

ダーツにはさまざまな遊び方やゲーム形式があり、目的やプレイヤーのレベルに応じて選ぶことができます。ここでは、特に初心者が押さえておきたい基本的なゲームの種類を紹介します。
代表的なゲームが「01(ゼロワン)」です。これは301・501・701など、決められた点数からスタートし、最終的に0点ちょうどでフィニッシュすることを目指す競技です。得点力や計算力が求められ、シンプルながら奥の深いゲームとして広くプレイされています。
次に「クリケット」は、15〜20とブルのナンバーを使って得点とクローズ(3回命中)を競う戦略的なゲームです。特定のナンバーで点数を稼ぎつつ、相手が点を取れないように妨害する要素もあり、読み合いの面白さがあります。
他にも、すべてのナンバーを順に狙う「ラウンド・ザ・クロック」や、ダブルやトリプルだけを使う練習向けのゲームなども存在します。また、パーティー向けにカスタマイズされたミニゲームや、カウントアップと呼ばれる単純に得点を積み重ねる形式も人気です。
こうしたゲームを通じて、楽しみながらスロー精度や得点力を養うことができます。初めての方は、まずはカウントアップや01ゲームから始めると、ルールも簡単で安心です。
このように、ダーツは「的に当てる」だけでなく、多彩なゲーム性が魅力です。目的に合ったゲームを選ぶことで、飽きずに長く楽しむことができます。
関連記事はこちら
なお、ホワイトホースと並んで注目されるアワードに「ハットトリック」があります。狙い方や練習方法を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
→ ダーツ ハットトリック達成への道:技術と戦略
ダーツのホワイトホースと は何かを理解する総まとめ
- ホワイトホースはクリケット限定の最難関アワード
- 条件は1ラウンド内に異なる3つのトリプルを命中させること
- 成功には高い精度と冷静な判断が必要
- 名前の由来にはメリーゴーランド説や急流説がある
- 異なるトリプルを狙うためターゲット切り替え技術が求められる
- 同じナンバーを2回以上狙うと条件から外れる
- クローズ済みのナンバーはホワイトホース対象外となる
- スリーインザブラックはブルに3本で得られる別のアワード
- スタッツはPPDとMPRが最重要指標
- 用語理解はルールや戦術の習得に直結する
- オーバーキルは200点以上差での加点が無効となる状況
- バーストは01ゲームでスコアが超過し無効になる仕組み
- 大会では静かに待つ・道具を勝手に触らないのが基本マナー
- スランプ時はフォームと意識の見直しが有効
- スティールとソフトはルール・ボード・雰囲気が異なる
- ゼロワン・クリケット・カウントアップなど多彩なゲームがある
