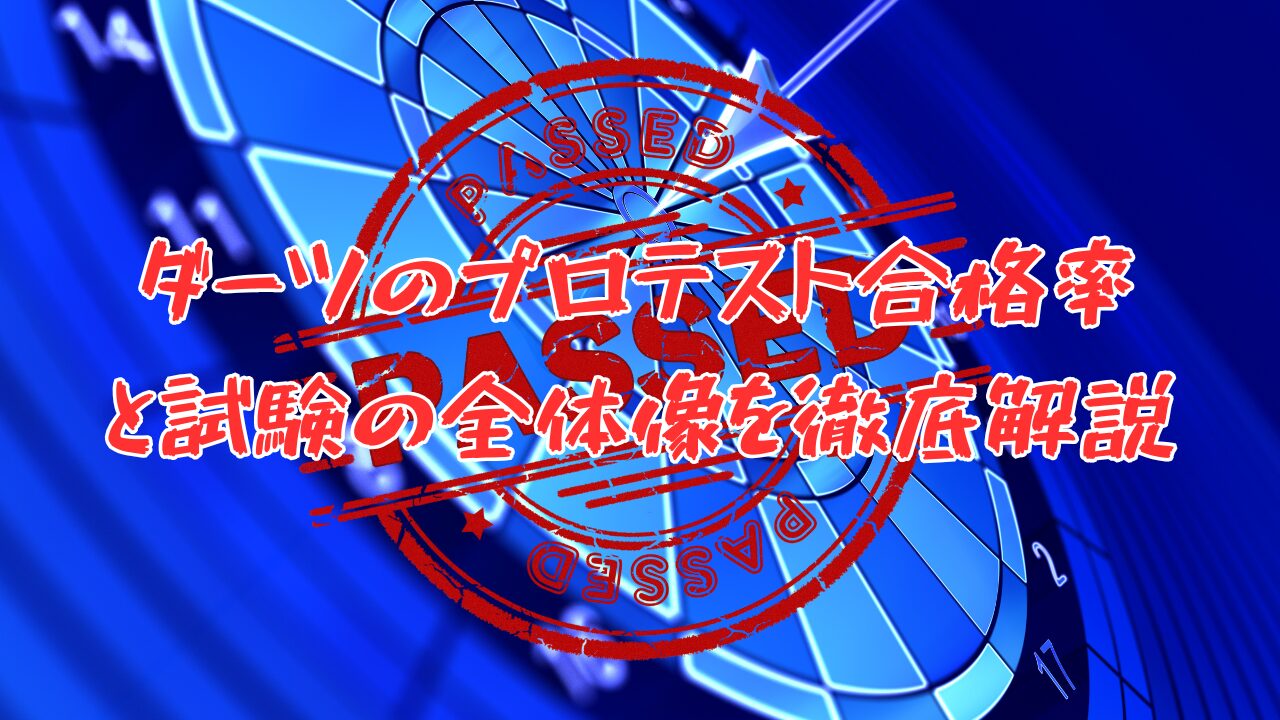
ダーツのプロを本気で目指すなら、「ダーツのプロテスト合格率」がどれくらいなのか、まず最初に知っておきたいポイントではないでしょうか。本記事では、ダーツプロになるにはどんなステップを踏む必要があるのかをはじめ、プロテストの内容や合格ライン、さらには試験レーティングの基準と目安など、合格に必要な実力を詳細に解説します。
試験では、実技と筆記の両方が課され、それぞれに異なる対策が必要です。また、試験の費用や準備にかかるコストも事前に知っておくべき重要な情報です。合格しやすい人の特徴や、よくある失敗例を知ることで、効率的な準備にもつながります。
さらに、日本で一番上手いプレイヤーとされる有名選手の実績、プロダーツ界における得点平均と上手さの基準、プロのセッティングに使われるバレルやフライトの選び方など、現役プロの視点から見た情報も紹介します。
男子プロと女子プロの違いや、今活躍している選手の動向にも触れつつ、プロダーツ選手の収入源やお金のリアル事情、さらには実力だけでなく見た目や人気が与える影響についても掘り下げていきます。
これからプロの世界に挑もうとしている方に向けて、現実的かつ具体的な情報を集約したガイドです。プロの入り口として、ぜひ最後まで読んで理解を深めてください。
記事のポイント
- ダーツプロテストの合格基準や試験内容の全体像
- 合格に必要なレーティングや技術レベルの目安
- 受験や登録にかかる費用とその内訳
- 合格しやすい人の特徴や落ちやすい失敗パターン
ダーツのプロテスト合格率と試験内容の全体像

- ダーツプロになるにはどんなステップが必要?
- プロテストの内容とは?筆記・実技の詳細ガイド
- 試験レーティングの基準と目安はどれくらい?
- 試験の費用はいくらかかる?準備に必要なコスト
- 合格しやすい人の特徴とよくある失敗例
- ダーツのプロテスト合格率はどのくらい?
ダーツプロになるにはどんなステップが必要?
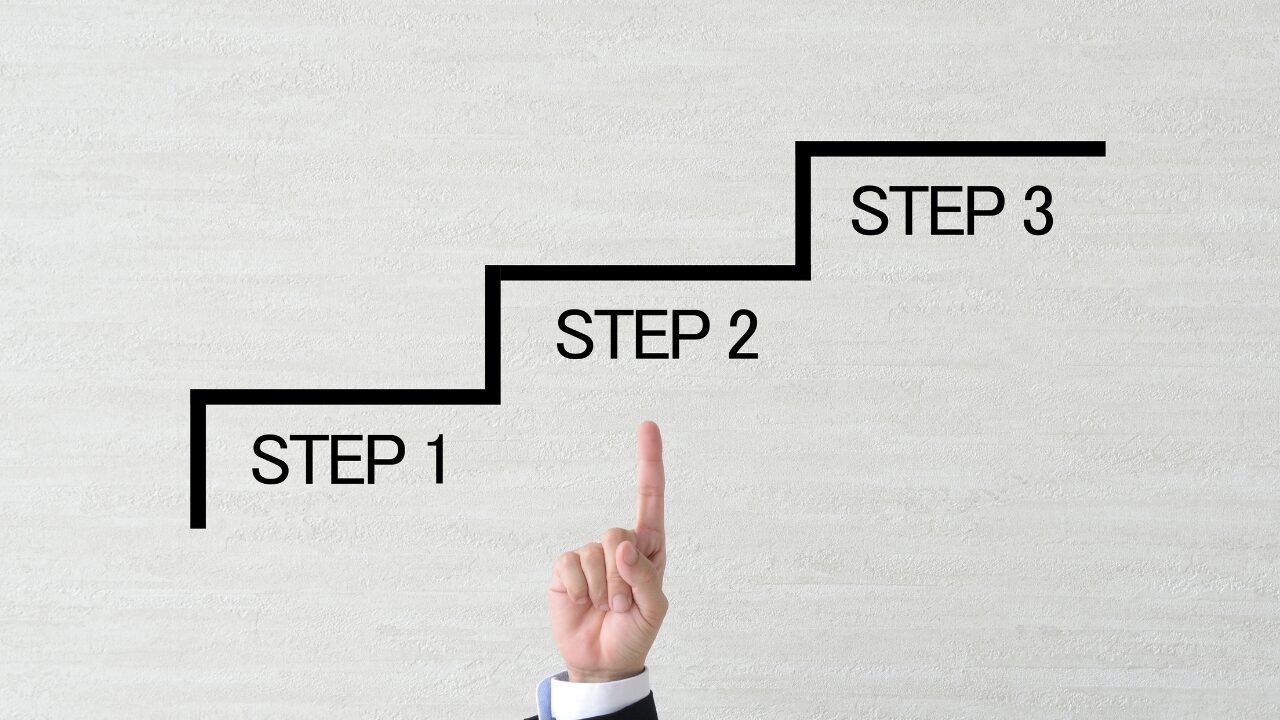
ダーツプロになるためには、プロ団体が実施するプロテストに合格し、その後、正式に選手登録を行う必要があります。手順自体はシンプルですが、内容を理解して準備しないと合格は難しいのが現実です。
まず最初に行うのは、どのプロ団体に所属するかの選択です。日本には主に「JAPAN」と「PERFECT」という2つの団体があります。それぞれ試験内容や合格難易度、活動スタイルが異なるため、自分に合った団体を選ぶことが重要です。
団体を決めたら、次に一次審査や申込手続きが必要です。PERFECTでは自己推薦文の提出が求められるなど、事前の書類審査があります。一方、JAPANは比較的自由に試験が受けられる仕組みです。
実技試験・筆記試験を受け、合格したら、登録料を支払い、必要書類を提出してプロ登録を行います。ここまで完了すれば、晴れてプロとしてツアーや大会に出場できるようになります。
ただし、プロになること自体がゴールではありません。プロとして活動するためには、資金や時間の管理、メンタル面の強化、継続的な練習環境の確保が不可欠です。このように、ダーツプロになるには試験対策だけでなく、長期的な視点での準備と覚悟が求められます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 団体を選ぶ | JAPANまたはPERFECTから、自分に合ったプロ団体を選択する |
| 2. 一次審査・申込 | PERFECTは自己推薦文などの書類審査あり、JAPANは自由申込制 |
| 3. 筆記試験の受験 | ルールやマナー、団体規約などに関する知識を問われる |
| 4. 実技試験の受験 | 各団体ごとの指定ゲームで技術力を評価される |
| 5. 登録手続き | 合格後に登録料の支払いと必要書類の提出を行う |
| 6. プロ登録完了 | プロとして公式戦やツアーへの参加が可能となる |
| 7. プロ活動の継続 | 練習、資金管理、メンタル強化など長期的な準備が必要 |
プロテストの内容とは?筆記・実技の詳細ガイド

プロテストの内容は、団体によって違いはありますが、基本的には「実技試験」と「筆記試験」の2つがセットになっています。それぞれの試験では、異なるスキルが求められます。
まず、実技試験ではプレイヤーとしての技術力が問われます。JAPANの試験では、「シュートアウトで5500点以上」「701を7ラウンド以内に2回フィニッシュ」「クリケットカウントアップでスタッツ5.1以上を2回」など、ハイレベルなスコア達成が求められます。一方、PERFECTでは「501を8ラウンド以内に1レグクリア(5回チャンス)」といった、やや現実的な設定ですが、会場の緊張感を伴う点で難しさがあります。
筆記試験では、ルールやマナー、団体の規約などが出題されます。JAPANの場合はオンラインでの受験が可能で、何度も挑戦できます。PERFECTでは記述式で小論文も含まれるため、準備不足だと落ちる可能性が高くなります。
また、両団体とも、試験前の書類提出や自己推薦文の記入が必要なケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
このように、プロテストは単なる技術試験ではなく、プレイヤーとしての総合力が試される場です。的確な準備と、実戦形式での練習を重ねることが、合格への鍵となります。
| 項目 | JAPAN | PERFECT |
|---|---|---|
| 実技試験内容 | シュートアウト:5500点以上 701:7ラウンド以内に2回フィニッシュ クリケットカウントアップ:スタッツ5.1以上を2回 |
501(ダブルアウト)を8ラウンド以内に1レグクリア(5回チャンス) |
| 筆記試験形式 | オンライン形式で何度でも受験可能 | 記述式、小論文あり |
| 筆記試験内容 | ルール、マナー、団体規約 | ルール、マナー、小論文 |
| 書類審査 | 不要(自由に受験可能) | 自己推薦文の提出が必要 |
| 試験の特徴 | 複数種目で高水準の実技が求められる | 実技は1種目のみだが緊張感が高い |
試験レーティングの基準と目安はどれくらい?

ダーツプロテストに合格するためのレーティングの目安は、団体によって異なります。一般的には「JAPAN」ではAAフライト以上、「PERFECT」ではAフライト以上が推奨されています。
まず、JAPANの場合は実技試験の難易度が高めに設定されており、シュートアウトや701、クリケットカウントアップといった複数種目を高水準でクリアする必要があります。特にシュートアウトで5500点以上や、701を7ラウンド以内に2回フィニッシュする条件などは、AAフライト以上の実力がないと厳しい場面が多いでしょう。
一方、PERFECTでは試験が1種目のみであるため、試験自体の難易度はやや低めです。501(ダブルアウト)を8ラウンド以内に1回クリアすればよいため、Aフライトの実力があれば合格圏内に入ります。ただし、周囲の視線が集まる中での実技となるため、メンタルの強さも必要です。
また、女子の場合は基準が若干緩和されており、Bフライト以上でもチャンスはあります。ただし、安定したスコアと試験内容に即した練習が不可欠です。
このように、フライトだけで合否が決まるわけではありませんが、少なくとも自分のレーティングがA〜AAに届いているかを一つの判断基準とすると、試験対策がしやすくなります。
| 項目 | JAPAN | PERFECT |
|---|---|---|
| 推奨レーティング(フライト) | AAフライト以上 | Aフライト以上 |
| 主な実技試験種目 | シュートアウト 701(7ラウンド以内に2回フィニッシュ) クリケットカウントアップ(スタッツ5.1以上×2回) |
501(ダブルアウト) 8ラウンド以内に1レグクリア(5回チャンス) |
| 試験の難易度 | 高め、複数種目で高スコアが必要 | やや低め、1種目のみだが集中力が問われる |
| 女子の目安フライト | Bフライト以上も可能(安定性重視) | Bフライト以上も合格例あり |
| メンタル面の要求 | 試験数が多いため集中力と持久力が必要 | 少ないチャンスで結果を出す精神力が必要 |
試験の費用はいくらかかる?準備に必要なコスト
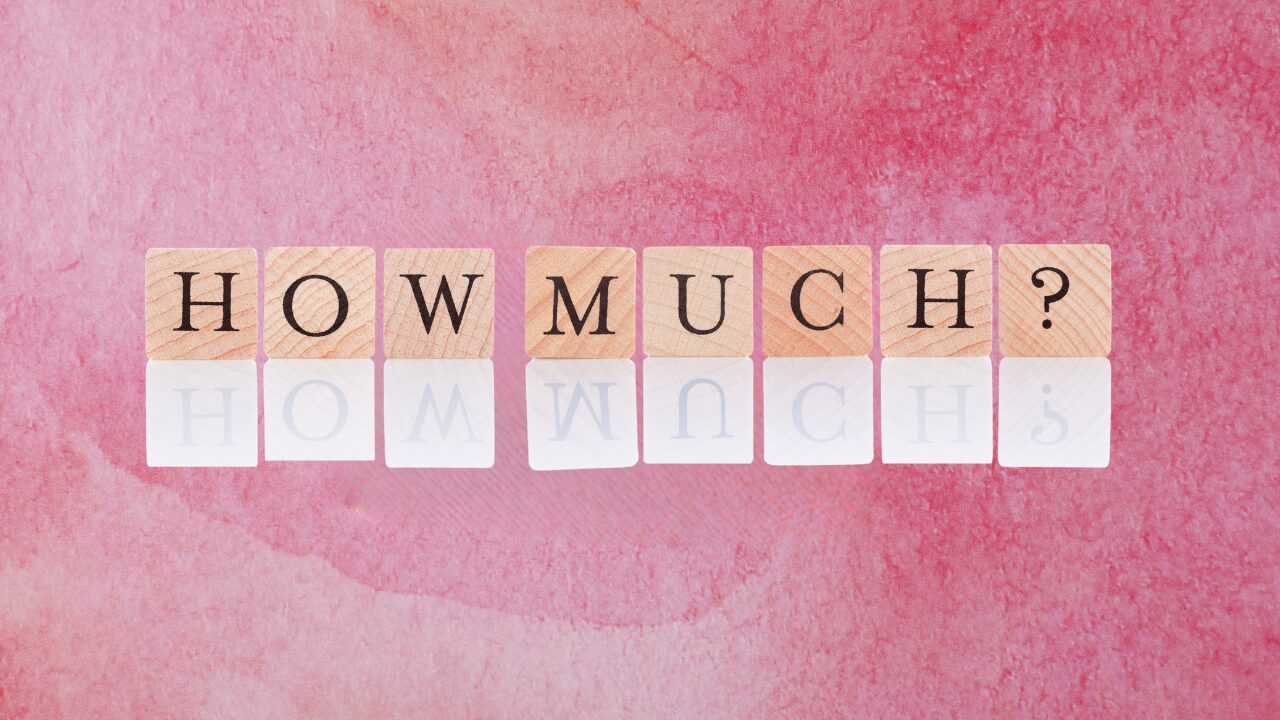
ダーツのプロテストを受けるには、受験料だけでなく登録費や試験のプレイ料金など、いくつかの費用が発生します。団体によっても費用構成が異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
例えば、PERFECTでは受験料が10,000円に設定されています。筆記試験・実技試験のどちらかを再受験する場合は5,000円が必要です。さらにプロ登録費として10,000円(4試合まで出場可能)または30,000円(全試合出場可能)を選択する形になります。合計では、最低でも約20,000円がかかります。
一方、JAPANでは少し複雑な費用体系です。試験のプレイ代が別途発生し、実技1回あたり100~200円程度。全てを最短で合格できた場合、700円程度で済みますが、平均的には1万円前後を想定しておくと安心です。加えて、登録料が30,000円、選手会費700円が必要になるため、トータルで約31,400円以上が必要となります。
この他にも、筆記試験を会場で受ける場合は会場使用料として3,000円程度がかかることもあります。実技試験のために店で練習するプレイ費や、遠方で試験を受ける場合の交通費も想定しておくべきです。
こう考えると、試験そのものの費用だけでなく、準備段階から数万円の出費は見込んでおいた方が良いでしょう。金銭的な準備も含めて、プロへの第一歩を計画的に進めることが重要です。
| 項目 | JAPAN | PERFECT |
|---|---|---|
| 受験料 | 無料(プレイ代別) | 10,000円 |
| 再受験料 | なし(何度でも受験可能) | 5,000円(筆記または実技) |
| プレイ代 | 実技1回あたり100〜200円 | 含まれる(会場で実施) |
| 筆記試験会場費(必要時) | 約3,000円 | 不要 |
| 登録料 | 30,000円 | 10,000円 or 30,000円(選択制) |
| 選手会費 | 700円 | なし |
| その他の費用 | 練習代・交通費など | 練習代・交通費など |
| 想定される合計費用 | 約31,400円以上 | 約20,000〜40,000円 |
合格しやすい人の特徴とよくある失敗例

ダーツプロテストに合格しやすい人には、いくつかの共通した特徴があります。一方で、受験者の中には同じような失敗を繰り返してしまうケースも少なくありません。ここではその両面を解説します。
まず、合格しやすい人の特徴として「練習環境を自ら整えている人」が挙げられます。自宅にダーツボードを設置して、日々の練習を継続している人は試験本番でも安定したパフォーマンスを発揮しやすい傾向があります。特に、PERFECTのような1発勝負の実技試験では、練習の質と量がそのまま結果に直結します。
次に、「試験形式を理解して対策している人」も有利です。JAPANの試験ではシュートアウトやクリケットカウントアップなど独自の種目が出題されるため、実際の試験形式に合わせた練習が不可欠です。普段の対戦ばかりしていると、本番で戸惑うことになります。
また、「緊張下でも力を発揮できる人」も強いです。実技試験では、周囲に人がいる状況でプレイするため、普段と同じ感覚で投げられないこともあります。事前に試験会場の下見をしたり、対人戦に慣れておくと、本番での緊張を和らげる効果が期待できます。
一方で、よくある失敗としては、「準備不足のまま受験してしまう」ことが挙げられます。特に筆記試験に関しては、「なんとかなるだろう」と軽視して臨むと、不合格になりやすいです。PERFECTではルールの暗記や小論文の提出も必要となるため、事前にしっかりと対策しておくことが求められます。
さらに、「実技試験中に焦ってしまう」ことも大きな落とし穴です。1レグ目で上がれなかっただけで動揺し、後のレグで本来の実力を発揮できなくなる受験者は少なくありません。途中で崩れてしまわないためにも、普段からミス後の立て直し練習をしておくと良いでしょう。
このように、合格する人は「知識」「技術」「心構え」の3つをバランスよく整えています。逆にどれか一つでも欠けてしまうと、試験でつまずくリスクが高くなると言えます。
ダーツのプロテスト合格率はどのくらい?

ダーツプロテストの合格率は、団体によって異なる傾向があります。特に「JAPAN」と「PERFECT」では、試験形式や内容に違いがあるため、合格のしやすさにも差が生じています。
まず、PERFECTに関しては、過去の公表情報や関係者の発信から、合格率は40〜60%前後と推定されます。この数字は、年や試験の実施場所によって変動があるものの、一定の実力を持った受験者がしっかり準備して臨めば、半数以上が合格できる可能性があるということを示しています。試験は501のダブルアウト1レグを8ラウンド以内にクリアするというもので、他の団体に比べて実技の構成がシンプルである点も、合格率を押し上げる要因の一つです。
一方で、JAPANのプロテストに関する合格率の正確な数値は公式には明かされていませんが、試験内容から見て、合格率はPERFECTよりも低いと推測されます。実技では、シュートアウト5500点以上や701の7ラウンド2回クリア、クリケットスタッツ5.1以上を2回など、複数のハードルを同時に超える必要があります。また、合格するまで何度でも受け直せる反面、内容が難しいため、1回の受験でクリアするのは簡単ではありません。
これらを踏まえると、受験者の合格可能性を見積もる上では、PERFECTは比較的挑戦しやすいが、JAPANは実技スキルが高くないと合格が難しいという理解が現実的です。どちらの団体を選ぶにせよ、自分の現在のレベルと照らし合わせて、適切な準備と戦略を立てることが合格への近道となります。
| 団体名 | 合格率の目安 | 実技試験の内容 | 難易度の特徴 |
|---|---|---|---|
| PERFECT | 約40〜60% | 501(ダブルアウト)を8ラウンド以内に1レグクリア | 内容はシンプルだが1発勝負の緊張感がある |
| JAPAN | 非公表(合格率は低めと推測) | シュートアウト5500点以上 701を7ラウンド以内に2回フィニッシュ クリケットカウントアップでスタッツ5.1以上を2回 |
複数種目を高精度でこなす必要があり難易度が高い |
ダーツのプロテスト合格率に関係する実力と環境

- プロダーツ選手の得点平均と上手さの基準とは?
- プロのセッティングはどう違う?バレルやフライトの特徴
- 男子プロと女子プロの違いとは?活躍選手も紹介
- プロになるとどんな名鑑や団体に登録される?
- 日本で一番上手いダーツプレイヤーは誰?
- プロダーツ選手の収入源とお金のリアル事情
- 実力だけではない?見た目や人気も影響する?
プロダーツ選手の得点平均と上手さの基準とは?

プロダーツ選手の「上手さ」を数値で表す場合、代表的なのが「得点平均(アベレージ)」と「スタッツ」です。これらは試合や実技試験での評価にも用いられ、上達度を客観的に判断する目安として活用されています。
まず、01ゲーム(例:501や701)での平均得点は非常に重要です。上位プロの多くは、1ラウンド(3投)あたり90点以上をキープしています。これは、ほぼ毎回トリプル20(T20)に入れている計算になります。中でも、JAPANの実技試験で要求される701の7ラウンドフィニッシュは、スタッツ100を超えるプレイが求められるため、実質的にAAフライト以上の実力が必要です。
一方、クリケットでは「スタッツ」という別の指標が使われます。こちらは1ラウンドで平均何マーク取ったかを表し、プロレベルでは5.0以上を目指すのが一般的です。JAPANの試験基準でも、5.1以上が2回求められており、この数値がプロとしての最低水準とされています。
単に得点を出すだけでなく、試合の流れを読み、安定して狙ったポイントに投げ続ける力が上手さの本質です。高スタッツを維持するためには、技術だけでなく集中力や試合勘も問われます。
このように、得点平均やスタッツはプロになるための具体的な基準であり、現在の実力を把握する有効な指標です。自分のデータを数値で把握することから、プロへの道が始まります。
プロのセッティングはどう違う?バレルやフライトの特徴
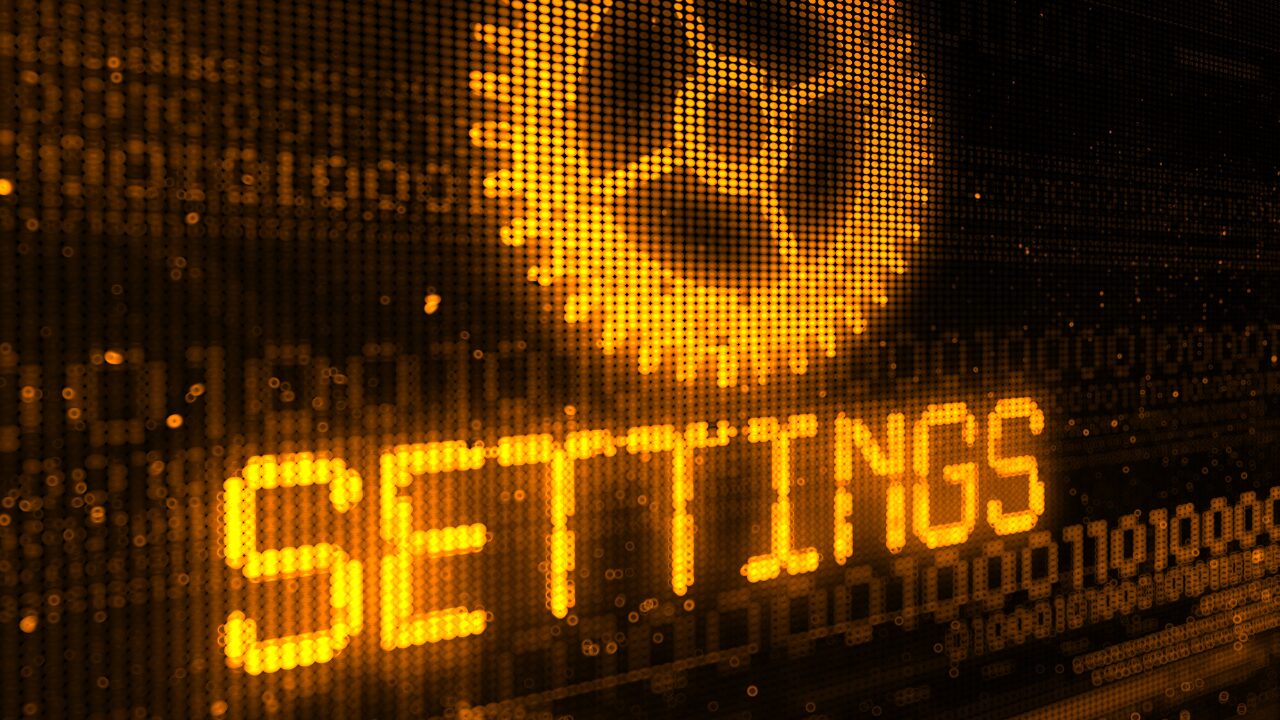
プロダーツ選手のセッティングは、見た目だけでなく性能面でも明確な特徴があります。バレルやフライトといった各パーツの選び方に、プロのこだわりが詰まっています。
まず、バレルについては「重心位置」や「重さ」「長さ」によって投げ心地が大きく変わります。多くのプロは、自分のフォームに合ったバレルを選ぶため、試投を繰り返して微調整を行っています。例えば、手元でしっかり押し出したい選手は重心が後ろのバレルを選ぶ傾向がありますし、シャープなスローを目指す人は細身で長めのバレルを好むことが多いです。
次にフライトですが、こちらも飛びの安定性に大きく関わります。プロの多くは、空気抵抗を考慮してシェイプやスリムといった細身のフライトを選びます。これにより、細かいグルーピングをしやすくなり、精度の高いプレーが可能になります。
また、シャフトの長さや素材もセッティングの一部です。軽量なカーボンシャフトやアルミ製を選ぶことで、全体のバランスを調整している選手も少なくありません。
重要なのは、「見た目がかっこいいから」という理由でセッティングを決めるのではなく、自分の投げ方やフォームに合っているかどうかです。プロはその感覚を非常に大切にしています。
このように、プロのセッティングは細部にまで配慮された調整の積み重ねでできており、性能を最大限に引き出す工夫がなされています。試合で結果を出すためには、技術だけでなくセッティングの最適化も欠かせない要素です。
男子プロと女子プロの違いとは?活躍選手も紹介

ダーツ界において男子プロと女子プロは、試験内容や大会の形式、そして競技人口の点で違いがあります。性別による単なる区分以上に、それぞれに合ったスタイルと環境が用意されています。
まず試験の内容に違いがあります。例えばJAPANプロテストでは、男子は701を7ラウンド以内にフィニッシュするのに対し、女子は501を6ラウンド以内にフィニッシュするというように、使用するゲームやラウンド数が異なります。また、クリケットの目標スタッツも男子より女子の方が少し緩めに設定されています。これは男女間の平均的なスタッツ差やプレイスタイルの違いを考慮した運営側の配慮です。
競技人口に関しても男子の方が多く、試合の規模や出場選手数に差があります。ただし、女子プロの中にも国内外で目覚ましい活躍をしている選手は多く、近年は実力差が縮まってきている印象もあります。
たとえば、鈴木未来選手は世界大会でも数々の好成績を残し、JAPAN男子プロの大会にも出場してベスト16入りを果たした経験があります。男子では有原竜太選手や浅田斉吾選手などが高い実力で知られており、年間ランキングでも常に上位に名前が挙がります。
このように、男女それぞれの試験と大会の枠組みは分かれていますが、活躍の場は広がりを見せています。性別を問わず、努力次第でトッププロとして名を馳せることができる環境が整ってきていると言えるでしょう。
プロになるとどんな名鑑や団体に登録される?

ダーツのプロテストに合格すると、選手は各団体が発行する公式名鑑に登録され、正式なプロ選手として活動することになります。これはプロとしての信頼性を示すとともに、スポンサーやファンからの認知にもつながる重要な要素です。
まず、日本には主に2つのプロ団体があります。「JAPAN」と「PERFECT」です。それぞれにプロライセンス制度があり、合格後は団体ごとのプロ名鑑に登録されます。この名鑑には選手名、所属エリア、戦績などが掲載され、一般公開されるケースも多く、閲覧したファンが選手を知るきっかけにもなっています。
JAPANの場合、選手名鑑の登録はプロとして活動するための条件の一つになっており、年間登録料を納めた上で掲載されます。PERFECTも同様に、登録後は名鑑への掲載が必須で、こちらも公式サイトなどで確認することが可能です。
名鑑への掲載によって得られるメリットは、単に情報が掲載されるだけではありません。スポンサー企業の目に留まりやすくなったり、イベント出演やメディア出演の声がかかることもあります。さらに、SNSやYouTubeでの活動と併せてプロモーション活動を行う選手も多く、名鑑はその基盤となります。
このように、プロになることで名鑑に登録され、ダーツプレイヤーとしての信頼性が形になるのです。それは同時に、競技者としての責任や影響力を持つ立場になることも意味しています。
日本で一番上手いダーツプレイヤーは誰?

誰が日本で最も上手いダーツプレイヤーなのかを一言で断定するのは難しいですが、実績に基づいて判断するなら、有原竜太選手が現在の代表格といえます。
有原選手は、2022年の「JAPAN」年間ランキングで堂々の1位を獲得しました。年間を通じて安定したパフォーマンスを続けた結果であり、その持続力と実力の高さが高く評価されています。瞬間的な勝利ではなく、長期にわたって上位を維持するのは、極めて困難なことです。
他にも、浅田斉吾選手や山田勇樹選手の名前は外せません。彼らは国内だけでなく、国際大会でも結果を残しており、世界基準で見ても実力者といえる存在です。特に浅田選手はPDC(プロフェッショナル・ダーツ・コーポレーション)の大会にも出場経験があり、国際的な評価も高いプレイヤーです。
最近では、酒井素選手のような新進気鋭の若手も台頭しており、国内の競技レベルは着実に上がっています。ランキング上位には、実力だけでなく安定性と経験を兼ね備えた選手が揃っています。
こうした背景から、有原竜太選手が「今、最も信頼性の高い日本一のダーツプレイヤー」とされるのは妥当でしょう。ただし、競技の世界は常に流動的です。今後の大会次第で勢力図が変わる可能性もあるため、注目し続ける価値があります。
有原竜太選手:JAPAN年間ランキング1位
有原竜太選手は、2024年の「SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN(JAPAN)」において年間ランキング1位を獲得しました。これは2022年に続く2度目の快挙であり、年間を通じて安定した成績を維持した結果です。特に、STAGE18ではPPD(1ラウンドあたりの平均得点)43.148、MPR(1ラウンドあたりのマーク数)5.907という高い数値を記録しました。
浅田斉吾選手:世界大会での優勝
浅田斉吾選手は、2024年5月に開催された「SUPER DARTS 2024」で優勝し、世界一の称号を手にしました。また、同年の「D-TOUR 2024 グランドスラム」でも優勝を果たし、国内外での実力を証明しました。
酒井素選手:若手の台頭
酒井素選手は、2024年のJAPAN年間ランキングで3位にランクインし、若手選手として注目を集めました。特に、STAGE8岡山では決勝で畦元隆成選手を破り、今シーズン初優勝を飾りました。
このように、2024年の日本ダーツ界では、有原竜太選手の安定した成績、浅田斉吾選手の世界大会での活躍、酒井素選手の若手としての台頭が際立ちました。これらの実績を踏まえると、現時点で「日本で一番上手いダーツプレイヤー」は有原竜太選手と評価されることが多いですが、他の選手たちの活躍も見逃せません。
プロダーツ選手の収入源とお金のリアル事情

プロダーツ選手の収入は、賞金だけに限られません。むしろ、複数の収入源を組み合わせて生計を立てているケースが一般的です。
まず中心となるのは、国内外の大会での賞金です。たとえば、JAPANやPERFECTの主要大会で優勝すれば、賞金は100万円以上に達することもあります。さらに年間ランキングの上位者には、ボーナスとして最大300万円の報酬が支払われる場合もあります。
次に大きな割合を占めるのがスポンサー収入です。プロ選手は自身が使用しているダーツブランドやスポーツ用品メーカーと契約することで、月額のサポートや製品提供を受けています。人気選手になるほど、この契約額も大きくなります。
他にもイベント出演料やメディア出演料、講師としてのレッスン収入などもあります。さらには、自身がオーナーやスタッフを務めるダーツバーの売上が、副収入として機能している選手も少なくありません。
一部のトッププロは、これらの収入を合わせて年収2000万〜3000万円以上を稼ぐこともあります。ただし、この水準に達するのはごく一部であり、多くのプロは副業と並行しながら活動を続けているのが現実です。
ダーツの実力に加え、セルフブランディングや発信力も問われる時代です。YouTubeチャンネルやSNSを活用することで収入を広げている選手もおり、収益構造は年々多様化しています。こうした現実を理解することで、プロダーツ選手の生き方がより鮮明に見えてくるはずです。
実力だけではない?見た目や人気も影響する?
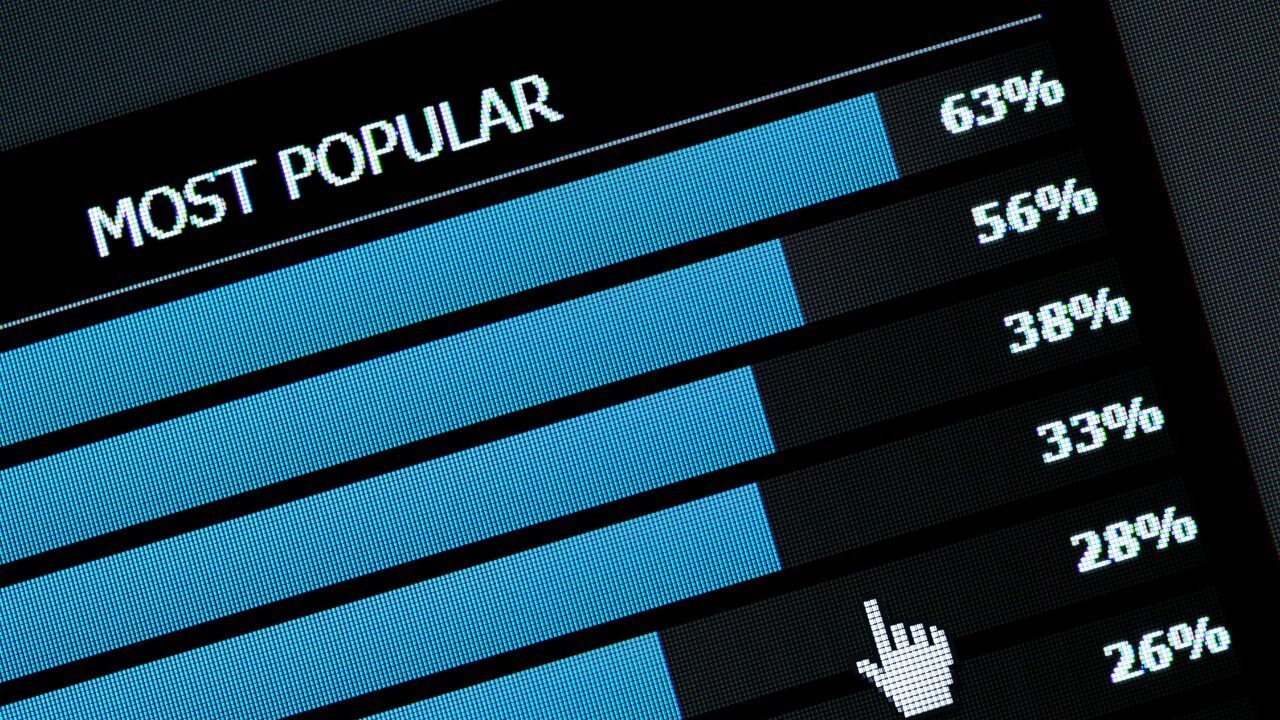
プロダーツの世界では、実力が第一であることに疑いはありません。ただし、近年は「見た目」や「人気」も選手の評価に影響を与える重要な要素になっています。
特にスポンサー契約やメディア露出の面で、その傾向が顕著です。企業はプロモーション効果を期待して選手と契約するため、ルックスや話題性、SNSでの発信力を重視するケースも少なくありません。実際、フォロワー数の多い選手はイベントや広告案件の依頼が増える傾向にあります。
また、見た目やファッションが注目されることで「顔が売れる」効果もあります。観客やファンに覚えてもらいやすくなり、それが試合会場での応援やオンラインでのグッズ販売にもつながっていきます。人気の高い選手は「ダーツアイドル」のような存在になり、試合以外の場面でも活躍の幅が広がります。
とはいえ、人気や見た目だけでは長くプロとして活躍するのは難しいのも事実です。あくまでベースには確かな技術と安定した戦績が求められます。加えて、自身の魅力をどう伝えるかが、現代のプロとしての価値を左右する時代になってきているのです。
つまり、実力を磨くことが第一ですが、外見やセルフブランディングも無視できない要素として意識しておく必要があります。これからプロを目指す方は、「プレイヤーとしてどう見られたいか」も含めて、自分のスタイルを確立していくと良いでしょう。
ダーツのプロテスト合格率に関わるポイントまとめ
- 合格には団体ごとのプロテストに通過する必要がある
- 日本の主要プロ団体は「JAPAN」と「PERFECT」の2つ
- 実技試験はJAPANが複数種目、PERFECTは1種目制
- 筆記試験はJAPANがオンライン、PERFECTは記述式
- JAPANではAAフライト、PERFECTではAフライトが目安
- 費用はJAPANで約3万円、PERFECTは2万円前後
- 実技のスコア基準はJAPANの方が高く設定されている
- 書類提出や自己推薦文が必要な場合がある
- 合格には練習環境と試験形式に沿った対策が不可欠
- メンタルの強さも合否に大きく影響する
- 実技試験中の焦りが失敗の原因となることが多い
- 登録後はプロ名鑑に掲載され公式に活動可能となる
- 得点平均やスタッツは合格判断の重要な指標となる
- セッティングも実力を引き出すための重要な要素
- 合格後も継続的な実力維持と自己管理が求められる
