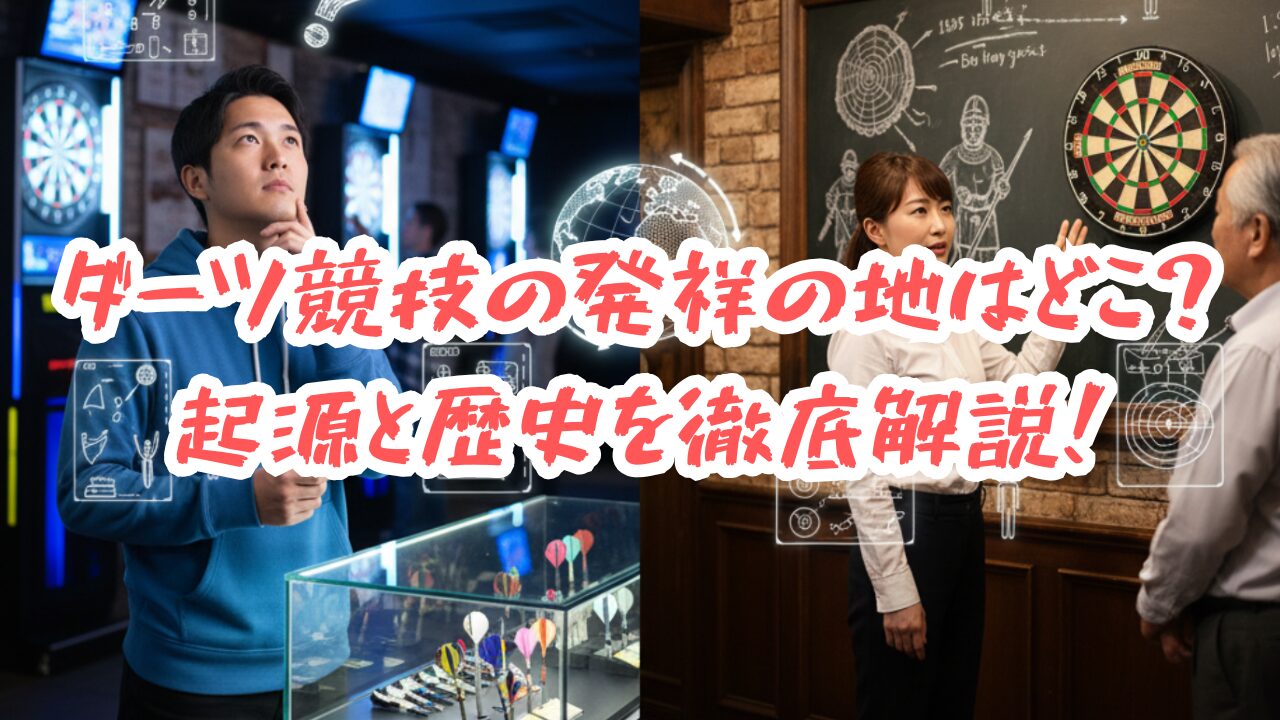
ダーツを楽しんでいると、ふと「ダーツ競技の発祥の地はどこなんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。ダーツはイギリス発祥という話は有名ですが、その詳しい起源や歴史、さらには名前の由来まで知っている方は少ないかもしれません。
ダーツの本場はどこで、現在ダーツが強い国はどこなのか、気になりますよね。また、実は現在主流のソフトダーツの発祥はイギリスではないという事実もあります。
この記事では、ダーツの起源から、日本におけるダーツの歴史、基本的なルールやボードまでのダーツ距離、そして競技を統括する世界ダーツ連盟に至るまで、あなたの疑問をすべて解決します。ダーツの矢一本一本に込められた、500年以上にわたる壮大な物語を紐解いていきましょう。
記事のポイント
- ダーツの起源とイギリスでの歴史
- ソフトダーツがアメリカで生まれた経緯
- 日本でのダーツの普及と発展の歴史
- 世界のダーツ強豪国や公式ルール
目次
ダーツ競技の発祥の地はどこ?その起源と歴史を解説

- ダーツの本場はイギリス!パブから生まれた歴史を解説
- 兵士の余興が起源?ダーツの始まりにまつわる有力な説
- 「Darts」の名前の由来と知られざる言語のルーツ
- 現在のダーツボードの原型が完成するまでの道のり
- 基本ルールの起源とスローイングラインまでの歴史的背景
ダーツの本場はイギリス!パブから生まれた歴史を解説

ダーツ競技の発祥の地、その揺るぎない答えは「イギリス」です。ダーツの歴史は500年以上前にさかのぼり、戦場で兵士たちが楽しんだ遊びがルーツとされています。
当初は弓矢を使った的当てゲームでしたが、次第に矢を短く削り、手で投げるスタイルへと変化しました。この手軽な遊びが、イギリスの文化に深く根付く「パブ」と共に庶民の間で爆発的に広まったのです。
パブは、単なる酒場ではなく、地域の人々が集う社交場であり、情報交換や娯楽の中心地でした。そこでダーツは、エールビールを片手に誰もが気軽に楽しめるゲームとして愛されるようになります。
厳しい冬の寒さから屋内で楽しめるスポーツとして定着し、やがて地域ごとのリーグ戦が開催されるなど、競技としての土壌も育まれていきました。
スポーツとして認められた日
しかし、ダーツの発展は順風満帆ではありませんでした。「酒場でやるゲーム」というイメージから、運任せのギャンブルではないかと見なされることもあったのです。1908年には、ダーツが運のゲームか技術のゲームかを争う裁判沙汰にまで発展しました。
この時、証言台に立ったあるパブのオーナーが、見事に20のダブルに3本のダーツを立て続けに入れ、「ダーツは運に左右されるゲームではない」と証明してみせたのです。この出来事をきっかけに、ダーツは晴れてスポーツとして公に認められることになりました。
パブがダーツの聖地となったのは、まさに必然だったのかもしれませんね。お酒を飲みながら仲間と盛り上がれるダーツは、パブの雰囲気にぴったりです。今でもイギリスの多くのパブにはダーツボードが設置され、人々の生活に溶け込んでいます。
このように、ダーツはイギリスのパブ文化と切っても切れない関係にあり、そこでスポーツとしての地位を確立し、世界へと羽ばたいていったのです。
兵士の余興が起源?ダーツの始まりにまつわる有力な説

ダーツの起源として最も有力な説は、14世紀から15世紀にかけてのイギリスの戦争中に、兵士たちが戦いの合間に行った余興から始まったというものです。
特に「百年戦争」や「バラ戦争」といった長期にわたる戦いの最中、兵士たちは士気を維持し、退屈を紛らわすために、武器であった弓矢を使って的当てゲームを楽しんでいました。
当初の矢は1メートル以上もあったとされ、それを弓で射って遊んでいましたが、より手軽に楽しむため、矢を短く切り、弓を使わずに素手で投げ合う競技へと変わっていきました。これが現在のダーツの矢(ダート)の直接のルーツとなったのです。
また、当時の的は、空になったワイン樽の底面や、大木を厚く輪切りにしたものでした。戦争中はワイン樽も貴重品だったため、木の輪切りが主な的として使われたようです。
ダーツ起源のポイント
- 時代:14~15世紀のイギリス
- 場所:百年戦争やバラ戦争の戦場
- 人物:イギリス軍の兵士たち
- きっかけ:戦いの合間の余興、的当てゲーム
- 道具の変化:長い弓矢から、短い手投げの矢へ
戦場という過酷な環境で生まれた遊びが、時代を経て洗練され、世界中の人々を熱中させるスポーツへと進化を遂げたことは、非常に興味深い歴史と言えるでしょう。
「Darts」の名前の由来と知られざる言語のルーツ

「ダーツ(Darts)」という名称の由来は、実は英語ではなく、古フランス語にあるとされています。古フランス語で「投げ槍」や「投げ矢」を意味する「dart」という単語が、そのまま英語に取り入れられ、競技名として定着しました。
この背景には、1066年のノルマン・コンクエストにより、フランス語がイギリスの支配階級の公用語となった歴史があります。多くのフランス語の単語が英語に流入し、"dart"もその一つでした。
もともとダーツは、兵士が武器を投げて遊んでいたことから始まっています。そのため、武器としての「投げ矢」を意味する言葉が、そのままゲームの名前に使われたのは自然な流れでした。
豆知識:ファイティングダーツ
歴史をさらにさかのぼると、6世紀のビザンティン帝国時代に「ファイティングダーツ」と呼ばれる約46cmの矢が存在したという記録があります。これは弓で射るよりも手で投げる武器として使われており、現在のダーツに近いものがありますが、競技ダーツの直接のルーツとは考えられていません。
一つの単語が言語の壁を越え、世界的なスポーツの名称として定着する。言葉の歴史もまた、ダーツの持つ奥深さの一つと言えるかもしれません。
現在のダーツボードの原型が完成するまでの道のり

ダーツがスポーツとして大きく飛躍するきっかけとなったのが、ダーツボードの進化です。当初、的として使われていた大木を輪切りにしたものは、天然の年輪が点数区分のガイドとなりました。
さらに使い込むうちに乾燥して表面に放射状の亀裂が入り、兵士たちはこの亀裂を新たな境界線として利用し、ゲームをより複雑で面白いものへと発展させたのです。
そして、ダーツの歴史における最も重要な出来事の一つが、1896年に起こります。イギリス人の大工であったブライアン・ガムリン氏が、現在のダーツボードに直接つながる点数区分を考案したのです。彼は、プレイヤーの技術がより試されるように、高い点数の隣に低い点数を配置しました。
例えば、最高得点の20点の両隣には、1点と5点という低い点数が置かれています。この絶妙な配置が、ダーツの戦略性を飛躍的に高めました。
ブリッスルボードの発明
ボードの素材にも大きな革新がありました。初期の木製ボードは、矢の刺さり具合を良くするために水に浸して使用されていましたが、異臭や劣化が問題でした。この問題を解決したのが、1935年にイギリスのノウドー社が発明した「ブリッスルボード」です。
船舶用ロープにも使われるサイザル麻を圧縮して作られたこのボードは、矢を抜くと繊維が元の位置に戻る自己修復機能を持ち、耐久性が劇的に向上しました。
ダーツボード進化の歴史
- ワイン樽の底:最も初期の的。
- 木の輪切り:年輪や亀裂が点数区分のヒントに。
- 点数区分の考案:1896年、ブライアン・ガムリン氏により現在の配置が考案される。
- ブリッスルボードの発明:1935年、サイザル麻を圧縮して作られたボードが登場し、耐久性が飛躍的に向上。
この点数システムとブリッスルボードの確立により、ダーツは単なる運任せの遊びから、高い技術と戦略性を要求される競技スポーツへと昇華しました。
基本ルールの起源とスローイングラインまでの歴史的背景

ダーツがスポーツとして確立される上で、ブライアン・ガムリン氏が考案した点数区分と同様に重要だったのが、統一されたルールの整備です。特に、投げる位置を示す「スローイングライン」の制定には、ユニークな歴史があります。
スローイングラインまでの距離は、現在スティール・ティップ・ダーツで237cmと定められています。(出典:公益社団法人 日本ダーツ協会 )この距離の由来には諸説ありますが、最も有名なのは、イギリスのパブに置かれていたビールケースを基準にしたという説です。
ビールケースが基準になった?
昔のパブでは、床に置かれた3つのビールケースの端から投げるのが一般的でした。そのビールケースの長さの合計が、現在のスローイングラインの距離の元になったと言われています。もちろん、これは俗説の一つに過ぎませんが、ダーツがパブ文化と共に育ってきたことを象徴する面白いエピソードです。
Oche(オキ)とは?
スローイングラインに設置される、一段高くなった仕切り板のことを「Oche(オキ)」と呼びます。プレイヤーはこれより前に足を踏み出してはいけません。語源ははっきりしていませんが、ダーツの公式な試合では必ず設置されています。
ルールが整備され、誰でも同じ条件下で競い合えるようになったことで、ダーツは公平なスポーツとして認められていきました。1924年にはイギリスで初の全国的なダーツ団体「National Darts Association」が設立され、競技としての基盤が固められていったのです。
現在では当たり前となっているルールや距離にも、先人たちの試行錯誤の歴史が詰まっていることが分かります。
ダーツ競技の発祥の地はどこ?現代までの発展と進化

- ソフトダーツの発祥はアメリカ!電子ダーツの誕生秘話
- ハードダーツとソフトダーツの歴史的な違いを比較
- 日本におけるダーツの歴史とブームの変遷
- ダーツが強い国と世界ダーツ連盟(WDF)の役割
- ダーツバーや競技大会で本場の雰囲気を体験しよう
- ダーツ競技の発祥の地はどこ?歴史の総まとめ
ソフトダーツの発祥はアメリカ!電子ダーツの誕生秘話

ダーツの発祥地はイギリスですが、現在日本で広く普及している「ソフトダーツ」の発祥の地は、実はアメリカです。1980年代、アメリカのメダリスト社が自動で点数計算を行う電子ダーツマシンを開発したことが、ダーツ界に革命をもたらしました。
それまでのダーツは、金属製のティップ(針)を持つ「スティール・ティップ・ダーツ(ハードダーツ)」が主流で、点数計算は手動で行う必要がありました。特に01ゲーム(ゼロワンゲーム)での引き算や、ダブルアウトの計算は初心者にとって一つの高いハードルとなっていたのです。
しかし、マイクロプロセッサを搭載した電子ダーツマシンの登場により、誰でも気軽にゲームを楽しめるようになりました。
ダーツのイメージを変えたマシン
電子ダーツマシンは、ダーツのイメージを大きく変えました。伝統的なパブゲームという側面だけでなく、アワード(特定の高得点)が出た際の派手な音や光の演出が加わり、ゲームセンターにも設置されるなど、エンターテインメント性が飛躍的に向上しました。
また、ティップがプラスチック製になったことで安全性も高まり、ダーツがより幅広い層に受け入れられるきっかけとなったのです。
電子ダーツがもたらした革命
- 自動計算機能:面倒な計算が不要になり、初心者でもすぐに楽しめる。
- 安全性:ティップがプラスチック製のため、安全性が向上した。
- 演出効果:アワード(特定の高得点)が出た際の派手な音や光の演出が、ゲームを盛り上げる。
このエレクトリックダーツの発明を機に、ダーツは伝統的な「スティール・ティップ・ダーツ」と、新しい「ソフトダーツ」の二つの流れに分かれて、それぞれが独自の文化を形成しながら発展していくことになります。
ハードダーツとソフトダーツの歴史的な違いを比較

ダーツは大きく分けて、イギリス発祥の伝統的な「ハードダーツ」と、アメリカで生まれた電子式の「ソフトダーツ」の2種類があります。両者は矢の先端(ティップ)の素材が違うだけでなく、ルールやボードのサイズ、そしてプレイされる環境にも違いが見られます。
それぞれの特徴を理解することで、ダーツの奥深さをより一層楽しむことができます。主な違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | ハードダーツ(スティール・ティップ・ダーツ) | ソフトダーツ |
|---|---|---|
| 発祥地 | イギリス | アメリカ |
| ティップ素材 | 金属製(スティール) | プラスチック製 |
| ボード素材 | サイザル麻の圧縮材(ブリッスルボード) | プラスチック製(セグメント) |
| ボードサイズ | 13.2インチ(約33.5cm) | 15.5インチ(約39.4cm) |
| スローライン距離 | 237cm | 244cm |
| 主な特徴 | 静音性が高く、家庭での練習にも向いている。プロの世界大会も多数開催。 | 自動計算機能と華やかな演出が魅力。オンライン対戦も可能。 |
「ハードダーツ」は和製英語?
日本ではスティール・ティップ・ダーツのことを「ハードダーツ」と呼ぶのが一般的ですが、これは和製英語です。海外では「Steel-tip Darts(スティール・ティップ・ダーツ)」と呼ばれるのが正式です。
ソフトダーツが先に普及した日本で、区別するために「ハード」という言葉が使われるようになったようです。
日本におけるダーツの歴史とブームの変遷

日本にダーツが伝わったのは、1960年代前半と言われています。イギリスから来た船によって横浜の港に持ち込まれ、英国式パブや大使館などを中心に、外国人コミュニティの間でプレイされるようになりました。その後、1970年には任意団体として日本ダーツ協会が設立され、少しずつ日本人プレイヤーも増えていきました。
ソフトダーツブームの到来
日本のダーツシーンが大きく動いたのは、2000年代に入ってからです。アメリカから上陸したソフトダーツマシンが、ダーツバーやゲームセンター、ネットカフェに設置されるようになり、大きなブームを巻き起こしました。
特に、ICカードで個人の成績を記録できたり、ネットワークを通じて遠くの相手とオンライン対戦ができたりするダーツマシンの登場が、爆発的な普及を後押ししました。
株式会社ダーツライブの調査によると、2023年時点での日本のダーツの推定プレイ人口(1年以内にプレイした人)は595万人にものぼり、日本の21人に1人がダーツをプレイしたことがあるという結果になっています。
スポーツとしての地位確立
2007年にはソフトダーツのプロ団体が設立され、現在では「JAPAN」と「PERFECT」という2大プロツアーが年間を通じて開催されています。さらに、2018年にはソフトダーツマシンが風営法の対象外となり、ダーツが「遊技」ではなく「スポーツ」として社会的に認められる大きな一歩となりました。
手軽さとゲーム性の高さから、ダーツは若者を中心に人気が拡大し、ダーツバーに長蛇の列ができるほどの社会現象にもなりました。現在では学生やファミリー層にも広がり、幅広い世代に愛されるスポーツとなっています。
ソフトダーツの普及によって競技人口が増えたことで、伝統的なスティールダーツにも再び注目が集まるようになり、現在では両方を楽しむプレイヤーが非常に多くなっています。
ダーツが強い国と世界ダーツ連盟(WDF)の役割

ダーツが最も盛んで、強い国と言えば、やはり発祥の地であるイギリスが挙げられます。プロのトッププレイヤーの多くがイギリス出身であり、賞金総額4億円以上を誇る世界最高峰の大会「PDC ワールド・ダーツ・チャンピオンシップ」は毎年ロンドンで開催され、絶大な人気を誇ります。
また、近年ではオランダがイギリスに次ぐ強豪国として台頭しており、多くのスター選手を輩出しています。
競技を統括する世界ダーツ連盟(WDF)の役割
ダーツの国際的な普及と発展を目的として、1976年に世界ダーツ連盟(World Darts Federation / WDF)がロンドンで設立されました。WDFは、ダーツを世界的なスポーツとして統括する重要な役割を担っています。
WDF公式サイトに示される主な役割
- 世界70カ国以上のダーツ団体を会員として承認する
- 国際的な競技ルールの標準化と推進
- WDFワールドカップやワールドマスターズなどの世界大会を主催する
- ダーツのオリンピック正式種目化を目指す活動
日本もWDF設立の翌年である1977年に加盟しており、世界の一員としてダーツの発展に貢献しています。WDFの存在によって、ダーツは国境を越えたグローバルなスポーツとして成長を続けているのです。
もう一つの巨大組織「PDC」
現在のプロダーツ界では、WDFから独立した「プロフェッショナル・ダーツ・コーポレイション(PDC)」も大きな影響力を持っています。PDCはより商業的でエンターテインメント性の高いイベントを主催し、高額な賞金で世界のトッププレイヤーを集めています。ダーツ界はこの2大組織を中心に動いていると言えるでしょう。
ダーツバーや競技大会で本場の雰囲気を体験しよう

ダーツの長い歴史や文化を知ると、実際に矢を投げてみたくなりませんか。現在、ダーツは非常に身近なスポーツになっており、初心者でも気軽に楽しめる場所がたくさんあります。
最も手軽なのは、全国にあるダーツバーやネットカフェ、ラウンドワンのような複合アミューズメント施設です。多くの店舗には「ハウスダーツ」と呼ばれる貸し出し用のダーツが用意されているため、手ぶらで行っても問題ありません。お酒や食事を楽しみながら、仲間とワイワイ盛り上がることができます。
初心者におすすめのゲーム
- カウントアップ:投げたダーツの合計得点を競うシンプルなゲーム。自分の実力を測るのに最適です。
- クリケット:特定の陣地を取り合う戦略的なゲーム。ダーツの奥深さに触れられます。
少し慣れてきたら、お店が主催する「ハウストーナメント」に参加してみるのもおすすめです。様々なレベルの人が参加するので、自分の実力を試したり、ダーツ仲間を作ったりする絶好の機会になりますよ。まずは気軽に一本、投げてみてはいかがでしょうか。
ダーツは年齢や性別、体格に関係なく、誰もが同じ土俵で楽しめるのが魅力です。2021年には「生涯スポーツとしてダーツを推進する議員連盟」も発足し、教育や健康増進の観点からも注目されています。
ダーツ競技の発祥の地はどこ?歴史の総まとめ

この記事では、ダーツ競技の発祥の地から現代に至るまでの歴史や文化について解説しました。最後に、記事の要点をまとめます。
- ダーツ競技の発祥の地はずばりイギリス
- 起源は14~15世紀のイギリス兵士の戦場での余興
- 当初の的はワイン樽の底や木の輪切りだった
- イギリスのパブ文化と共に庶民の間で広く普及した
- 1908年の裁判を経てダーツは技術を競うスポーツとして公認された
- ダーツの名前の由来はフランス語の「投げ矢」から来ている
- 1896年にブライアン・ガムリン氏が現在の点数区分を考案
- この点数配置の確立がダーツを競技スポーツへと進化させた
- 現在主流のソフトダーツの発祥の地はアメリカ
- 1980年代に自動計算機能を持つ電子ダーツマシンが開発された
- ハードダーツとソフトダーツではボードサイズや距離が異なる
- 日本へは1960年代に伝わり2000年代にソフトダーツブームが到来
- 現在のダーツ強豪国はイギリスやオランダ
- 1976年に世界ダーツ連盟(WDF)が設立され国際競技として発展
- ダーツは年齢や性別を問わず誰でも楽しめる生涯スポーツ
- ダーツバーやネットカフェで気軽に体験することができる
